DGPSといった場合、搬送波位相測位方式も含まれることになるが、まぎ らわしいばかりでなく、実情にも合っていないようである。今回はDGPSと いった場合にはコード測位方式の相対測位だけを示すこととした。
- 測位位置補正方式
基準局の既知位置と、そこでの単独測位結果を比較することによって位置の 補正値(緯度・経度・高度, もしくは三次元xyz直交座標系)を算出し、利用 者局の単独測位結果にその補正値を適用するもの。
基準局・利用者局双方において測位時刻が同じで、基線長があまり長くなけ れば(100 km 以下)、SAによる誤差、衛星軌道データの不正確さによる誤差、 電離層・対流圏による誤差等がほぼ同一のベクトルとなり、この操作を行うこ とによりある程度相殺され、測位精度が向上する。
この測位方式では、単独測位で使用した受信機がそのまま利用できることが 最大の長所であり、DGPS処理のための計算も非常に容易である。しかし、 基準局と利用者局双方で全く同じ組み合わせのGPS衛星を利用して測位して いなければならないという大きな制約がある。
トランスロケーション(translocation)という言葉が使用されることがあ るが、これは和製英語であり、日本国内でしか通用ない。また広義では搬送波 位相測位方式のことも示すようである。
- 擬似距離補正方式
基準局の既知位置と衛星から放送されてきた航法メッセージ中の衛星位置か ら計算した衛星までの「 正しい 」距離と、実際に基準局で測定された 擬似距離を比較することによって擬似距離補正値を算出し、利用者局で測定さ れた擬似距離にこの補正値を適用して測位を行う。
基準局で観測した衛星であれば、利用者局ではどの衛星を用いて測位しても よいという柔軟性がある。RTCM(Radio Technical Commission For Maritime Services: 米国海上無線技術委員会)規格ではこの擬似距離補正方式のため のフォーマットを扱っており、一般に普及している。以下に日本において整備 されている2大ディファレンシャル サービスを示す。
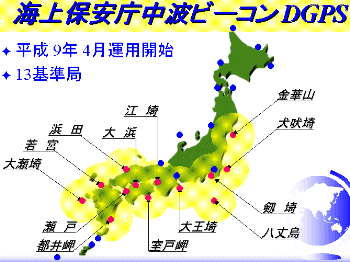
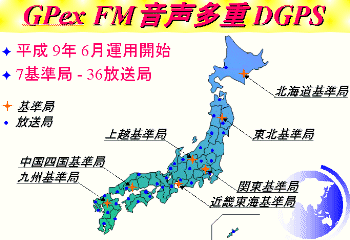
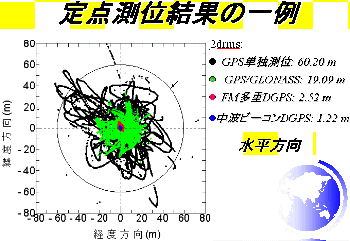
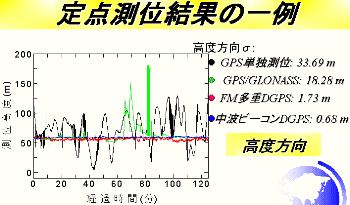



Copyright by Hiromune NAMIE
2000年 7月 18日 作成