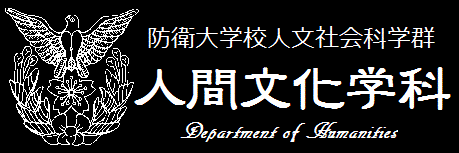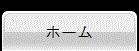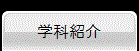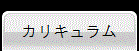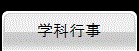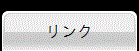水野 博太(Hirota Mizuno) 講師

最終学歴
2021年 東京大学大学院人文社会系研究科東アジア思想文化専門分野博士課程修了
学位
博士(文学)2021年1月 「大学と漢学 東京帝国大学とその前身校における漢学および「支那哲学」の展開について」
教育科目等
古典学概論、日本古典学特論、言語文化論、言語と文化、漢文学
専門分野
日本思想史、中国思想史
キーワード
儒教、漢学、中国哲学、学術史
主要所属学会
日本思想史学会、中国社会文化学会、日本儒教学会、日本中国学会
著書・論文等
1.『「支那哲学」の誕生 東京大学と漢学の近代史』(東京大学出版会、2024年)
2.「服部宇之吉と狩野直喜 「支那学」の光と影」(分担執筆、朱琳・渡辺健哉編『近代日本の中国学 その光と影』勉誠社、2024年)
3.The Invention of "Chinese Philosophy": How Did the Classics Take Root in Japan's First Modern University?(分担執筆、Handbook of Confucianism in Modern Japan (Edited by Shaun O'Dwyer), Japan Documents (MHM Limited), 2022)
4.「井上哲次郎の東洋哲学と服部宇之吉の儒教倫理」(分担執筆、牧角悦子・町泉寿郎編『講座 近代日本と漢学 第4巻 漢学と学芸』戎光祥出版、2020年)
5.「井上哲次郎における「日本哲学」の存在証明とその失敗」(日本思想史学会編『日本思想史学』第52号、2020年)
教官からひと言
日本思想史と中国思想史を専門分野としています。学部から大学院まで、中国思想系の専攻において、儒教を中心とした東アジア思想史を学びました。個人の研究としては、特に近代日本における儒教の展開について関心を持っていますが、教育ではそこに捉われず、広く日本思想史・中国思想史に関するテーマを柔軟に取り扱います。
近代以前の東アジア(日本・中国を含む)において、儒教は最も正統かつ最も広範に学ばれた思想・学問でした。たとえば幕末に育った渋沢栄一は、学問で身を立てた訳ではありませんが、当時の多くの青少年と同様、儒教を中心とした漢学を学んでおり、それが晩年の『論語と算盤』の伏線になっています。あるいは幕末の志士たちを「尊王攘夷」へと突き動かした「(後期)水戸学」と呼ばれる思想がありますが、そのバックボーンは明らかに儒教です。また吉田松陰は、野山獄での拘禁中に『孟子』を講義し、その翌年に松下村塾を作りますが、維新の元勲はそこで作り出されたのでした(その講義は『講孟余話』として残されています)。近代日本を作り上げた人々の知的背景には儒教があったのですから、近代日本を考える上でも、彼らが知的バックグラウンドとして有していた儒教について考えることは重要です。
儒教には、今なお有用な要素もあるでしょうし、それを自衛隊や一般社会における統率・自己修養等に活かす余地も、大いにあると思います。ただし、儒教(あるいは特定の思想)を学ぶことは、必ずしもそれに盲目的に賛同・服従することを意味しません。むしろ儒教、ひいては思想史を学ぶことで、これまで「当たり前」だと思っていたものが、実は特定の思想史的文脈・来歴に起因することが分かるということ、つまりその「当たり前」は、天地開闢以来そうであった訳ではないし、また未来永劫変えてはならないものではないことに気づけるということ、そのための柔軟な視野を養うということが、思想史ひいては人文学の魅力であり、役割であると思います。