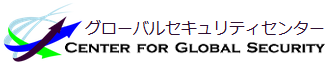中国の海洋進出、北朝鮮の核開発を挙げるまでもなく、アジアの安全保障環境は混迷の度を増しています。それに対して防衛省・自衛隊の役割も深化、多様化しています。それは2015年の日米防衛協力のガイドラインとそれを受けて成立した平和安保法制に示されているとおりです。
グローバルセキュリティセンター(GS)では、アジアの安全保障に関する研究を深め、その成果を自衛隊に還元すべく防衛省・自衛隊の研究アセットを動員したいと思います。政策志向的研究を念頭に置きながらも、その問題の根源的な要因を摘出すべく、基礎研究も疎かにしないよう留意し、地域研究、国際関係論、比較政治学など様々なディシプリンの研究者が共通の問題に取り組むことで、よい化学反応と相乗効果が生まれることを期待しています。
そのためにもGSのアジア安全保障研究では防衛省関係者はもちろん、問題の当事国の政策担当者、研究者との意見交換を実施し、より深い研究を進めます。