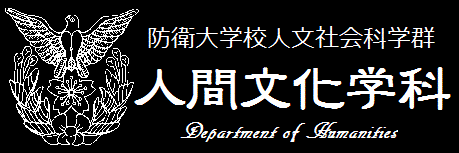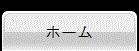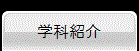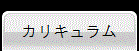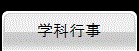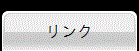木下 哲生(Kinoshita Tetsuo) 准教授

最終学歴
1991年 国際基督教大学大学院教育学研究科博士前期課程視聴覚教育法専攻修了
学位
教育学修士(1991年3月)
「外国語としての日本語学習の達成度に影響を与える要因についての実証的研究」
教育科目等
言語文化論、異文化コミュニケーション論、言語文化研究Ⅱ、日本語研究Ⅰ、日本語研究Ⅱ、日本語、異文化コミュニケーション概論
専門分野
コミュニケーション論、日本語学、教育学、日本文化論、異文化接触論
キーワード
コミュニケーション、異文化、教育、言語、外来語
主要所属学会
日本語教育学会、日本語学会、表現学会、比較文化学会、日本国語教育学会
著書・論文等
1.ことわざにうそはない?(アリス館、1997)
2.英語と意味のずれがある外来語(『現代日本語講座4語彙』明治書院、2002)
3.「バンド」と「ベルト」の意味の重なり―「洋装で腰につける帯」の場合―(『日本近代語研究3』ひつじ書房、2002)
4.日本人の異文化コミュニケーション―国際標準との差異にいかに対応するか―(『日本語教育学の視点』東京堂出版、2004)
5.文芸作品における外来語「スーツ」(『日本近代語研究 4』ひつじ書房、2005)
教官からひと言
私はこの人間文化学科で、異文化コミュニケーションと、日本と西欧のコミュニケーション理論や文化的背景はどのように異なるか、この2つを主題とした授業を行っています。
日本人は電車で席を譲ってもらっても「すみません」、ミスをした際にも「すみません」と言います。感謝と謝罪の言葉が同じなのはなぜでしょうか。また防大生へのアンケートで見てみると、一番心置きなく話せるのは「同性の友人」、そしてコミュニケーションで一番気を使っているのも「同性の友人」という結果が出ています。気兼ねしつつ気兼ねなく話せるはずの友人と話しているという矛盾した状況がなぜ起きてしまうのでしょうか。
これはすべて、日本人の「内向きコミュニケーション」という特性のためだと私は考えています。そして学生には、この特性が、決して海外では通用しないであろうことを、さまざまな理論を用いながら説明をしています。今や自衛隊は国内だけでなく、PKO活動を通して海外でも活躍しています。そして将来幹部自衛官となる皆さんたちに、「自分たちとは異なる文化」を持つ人々との交流の方法を身につけてもらいたいと考えています。