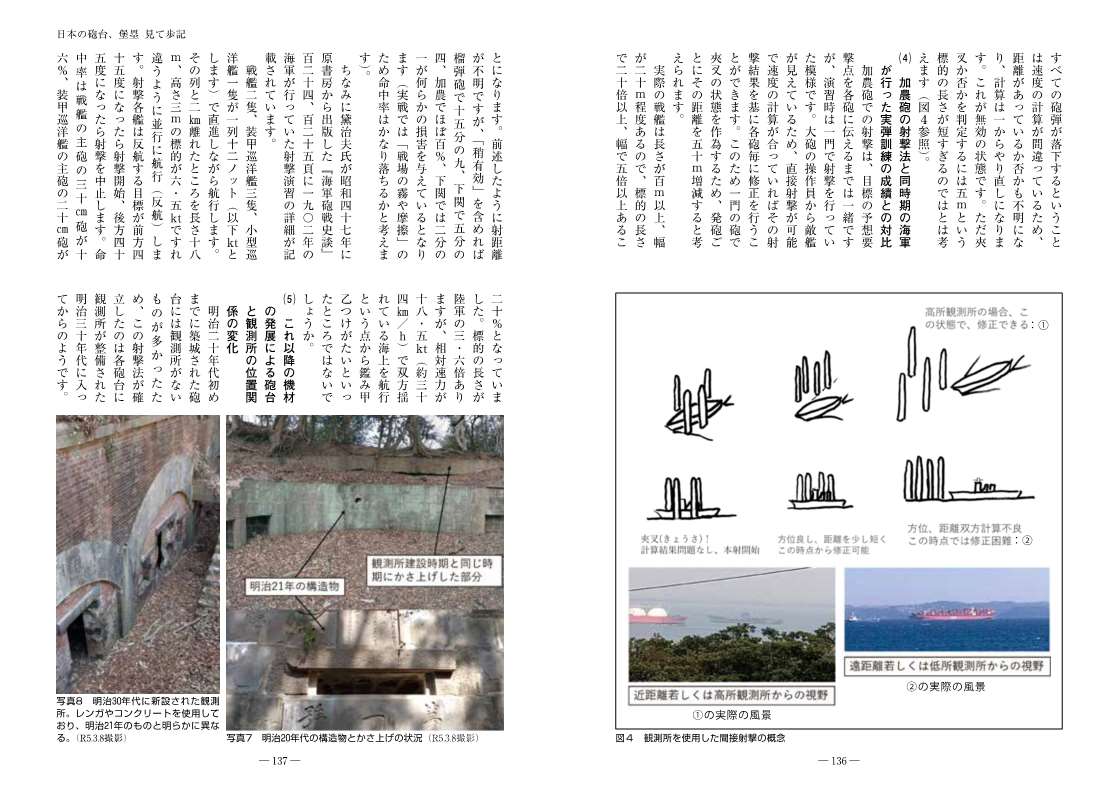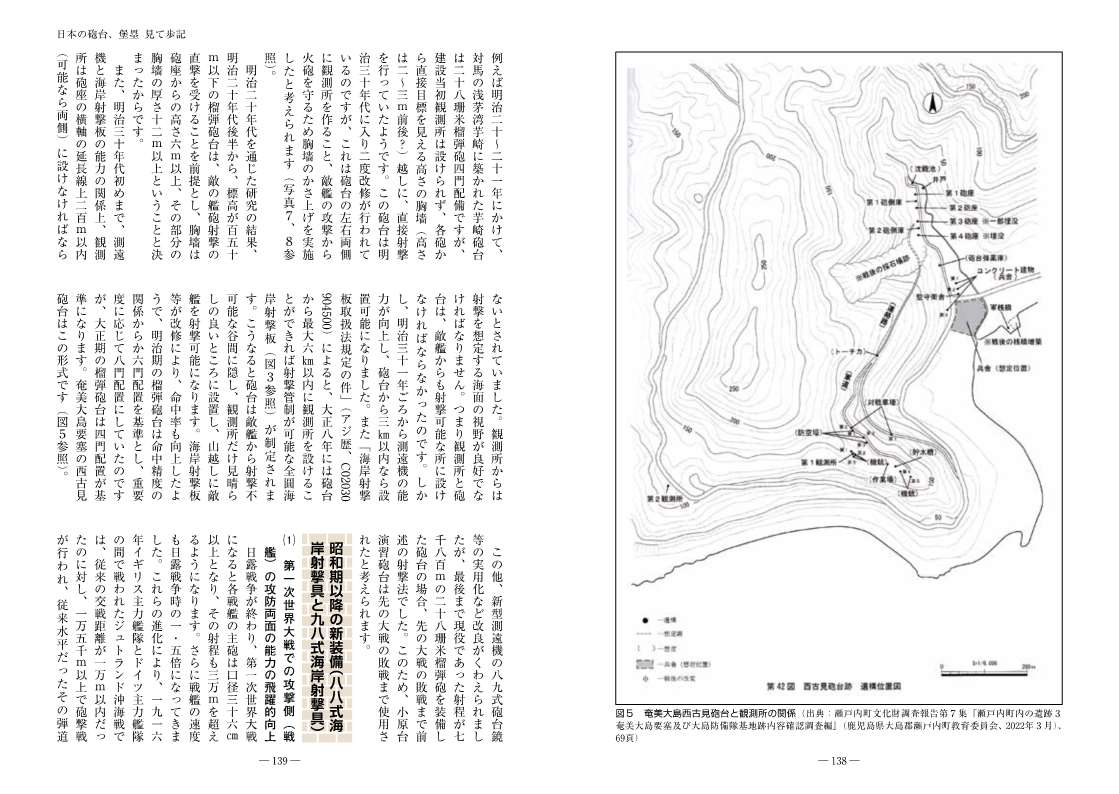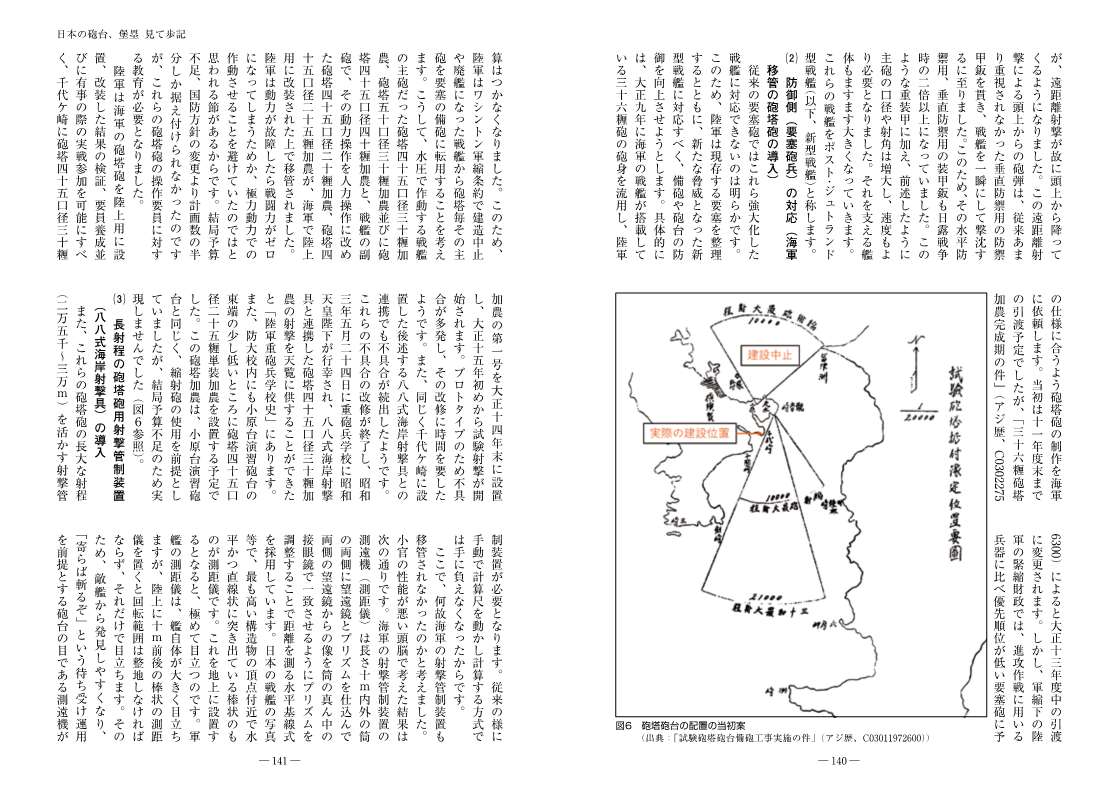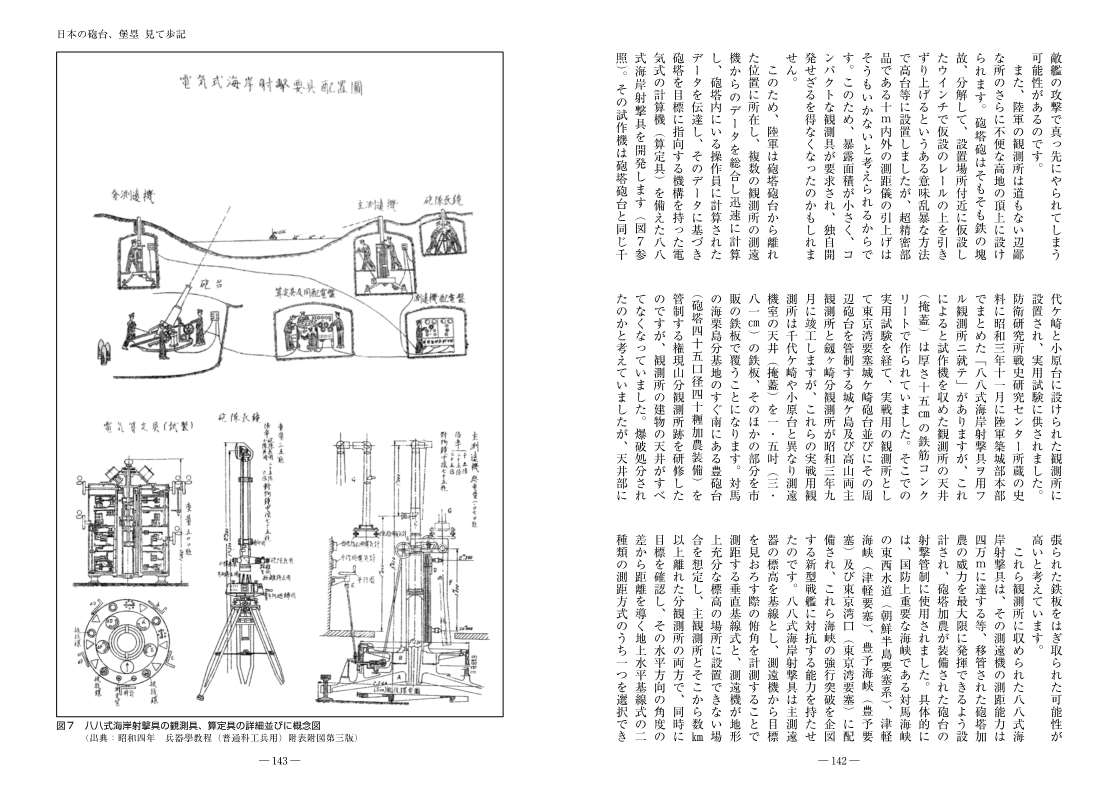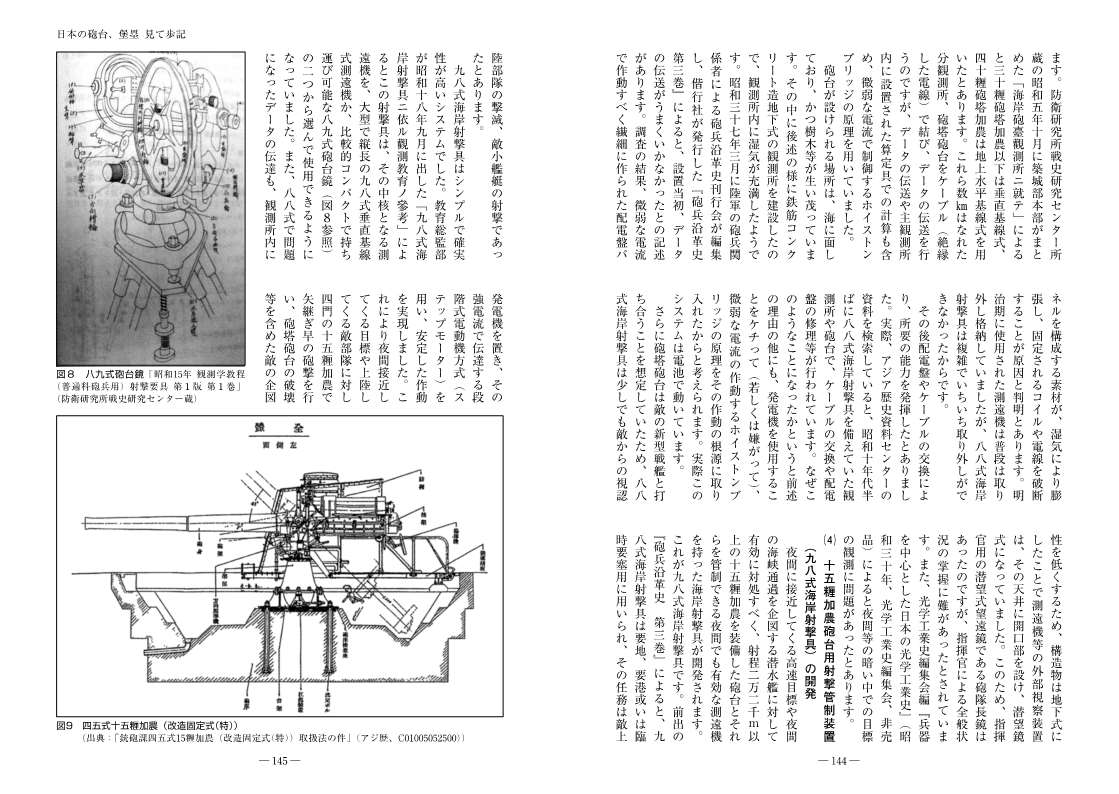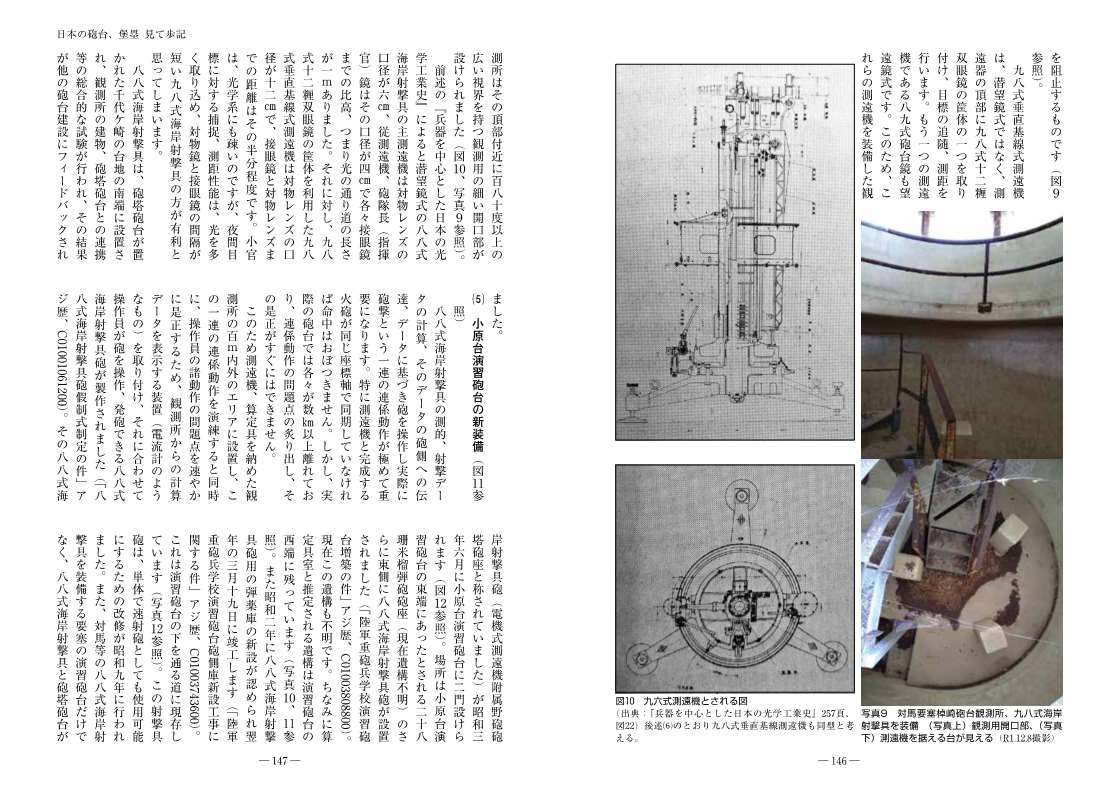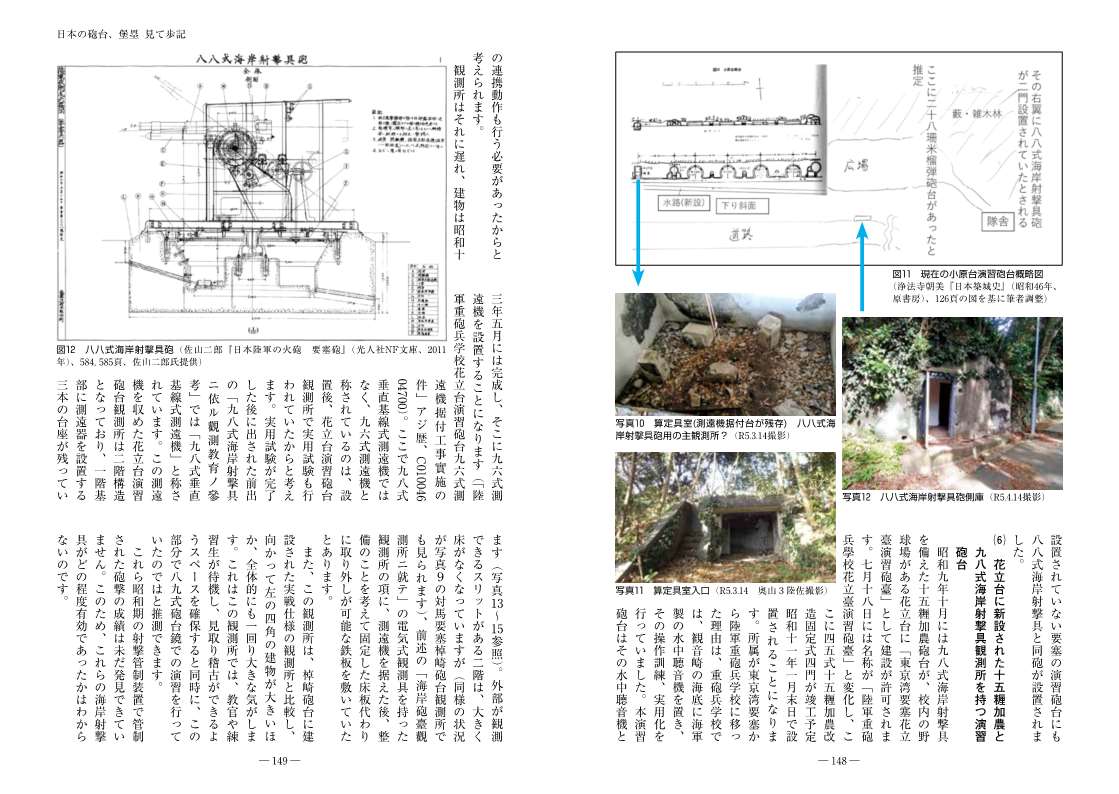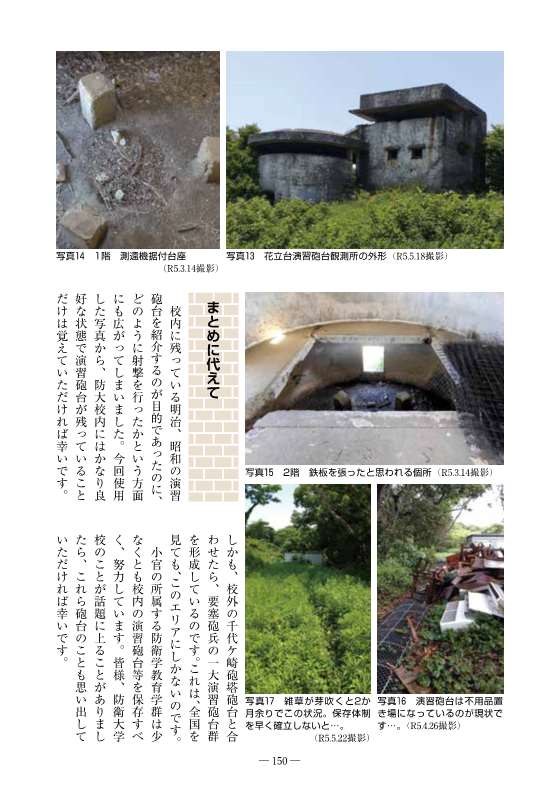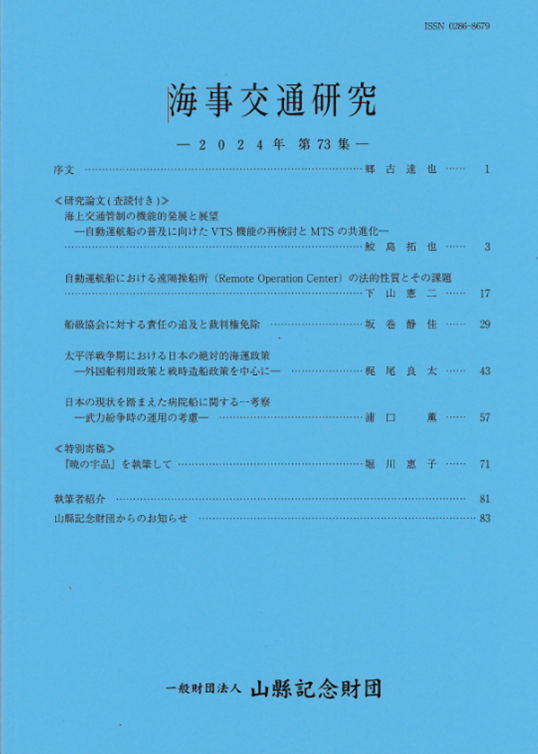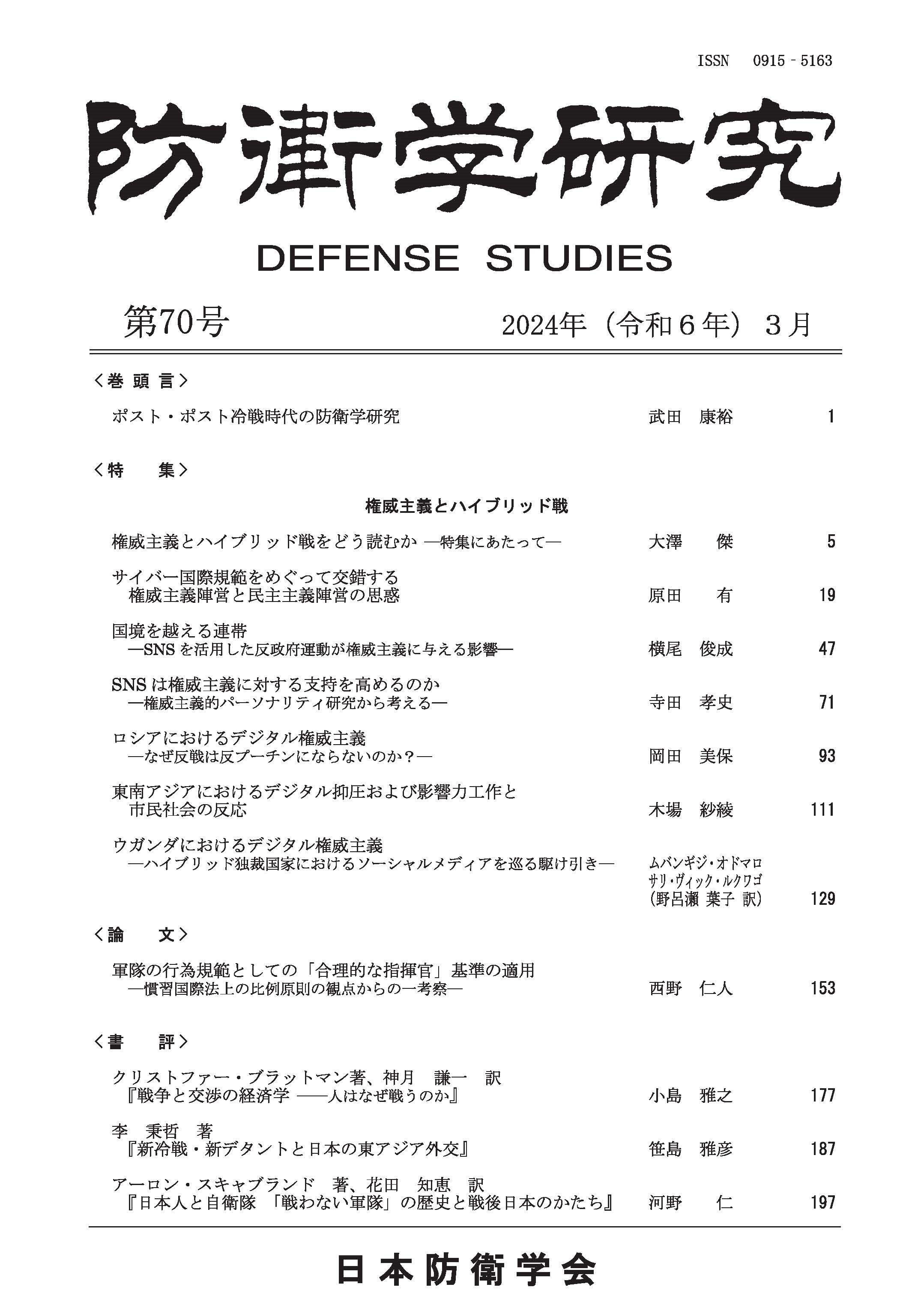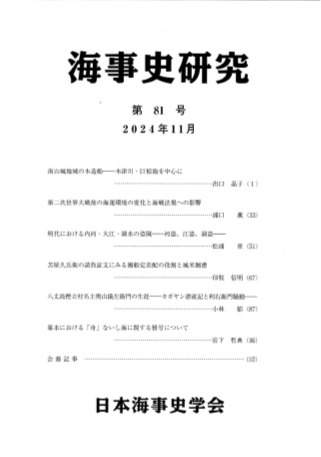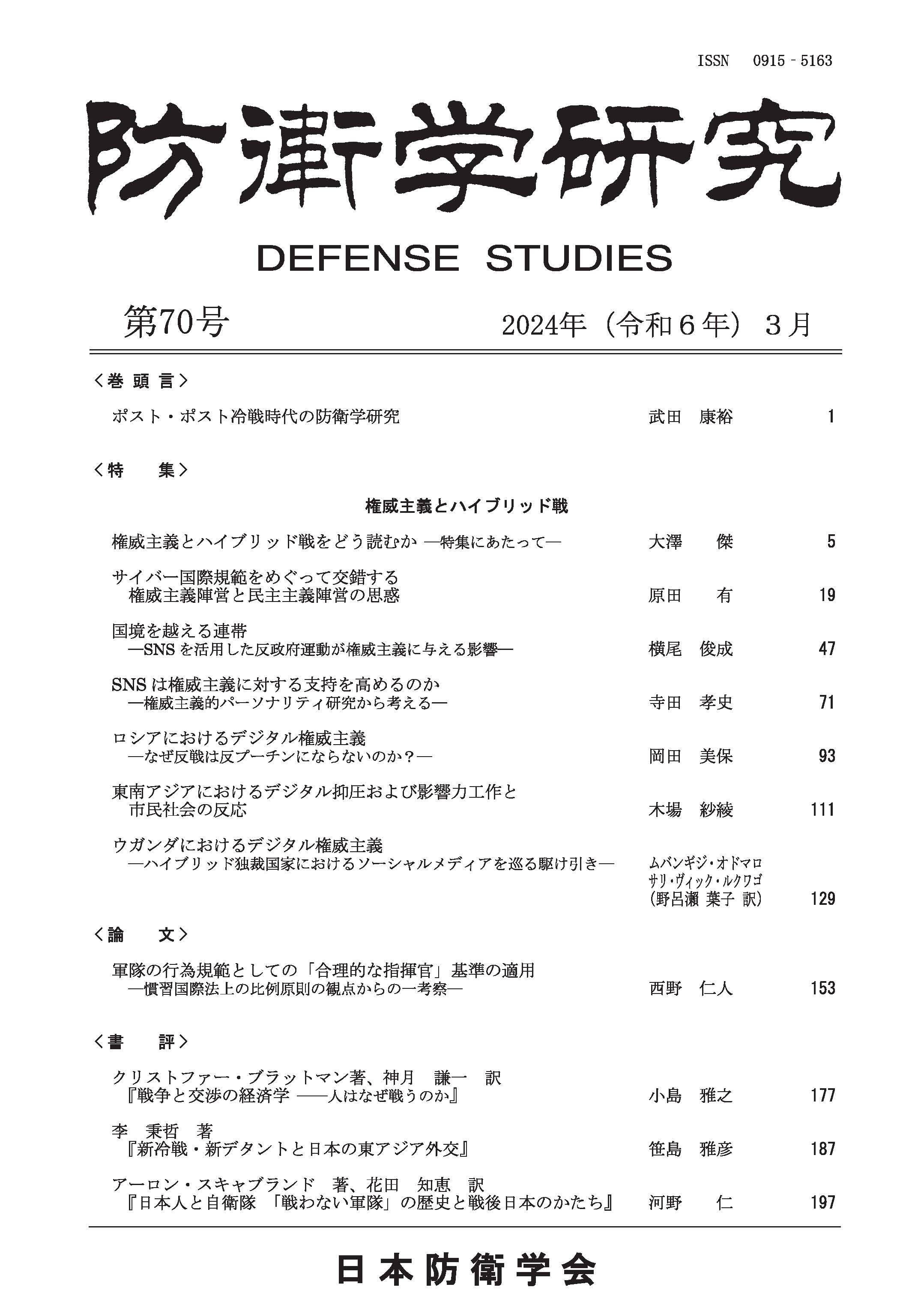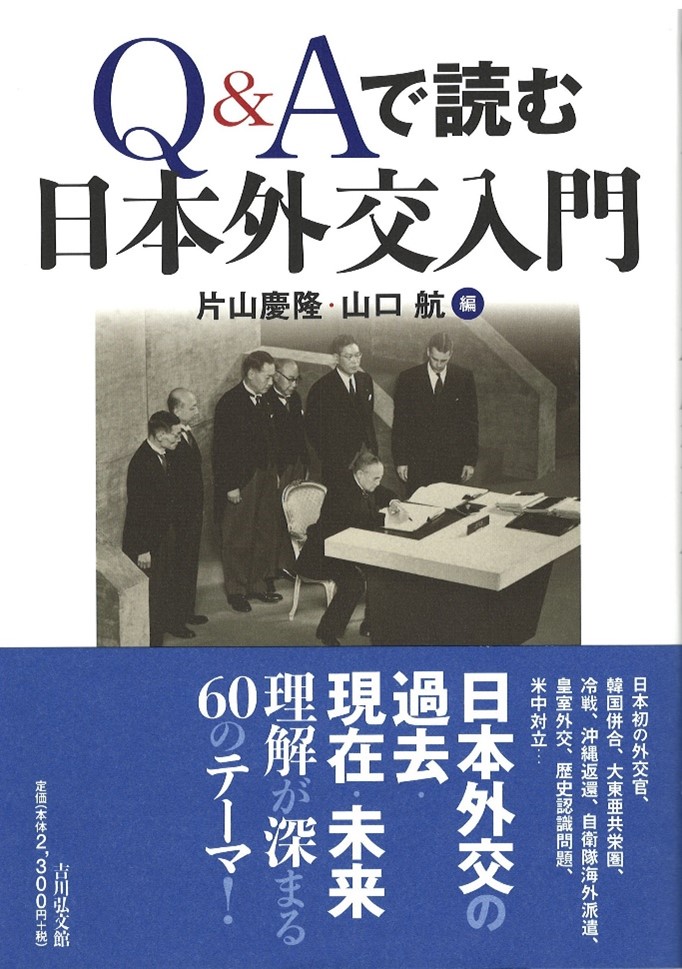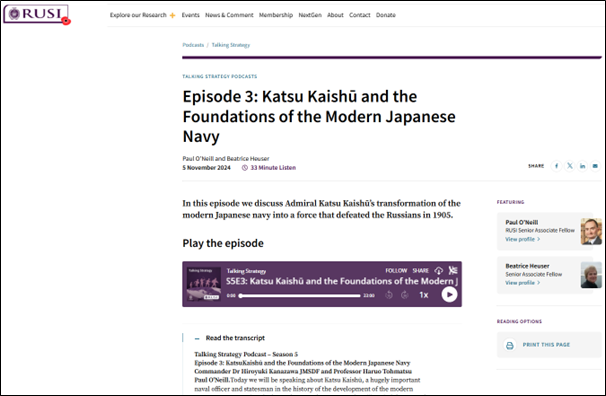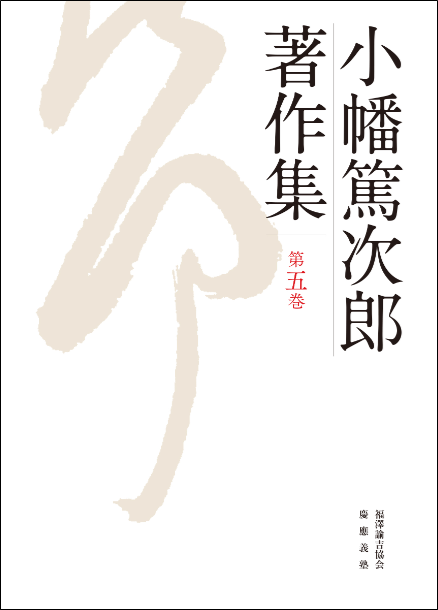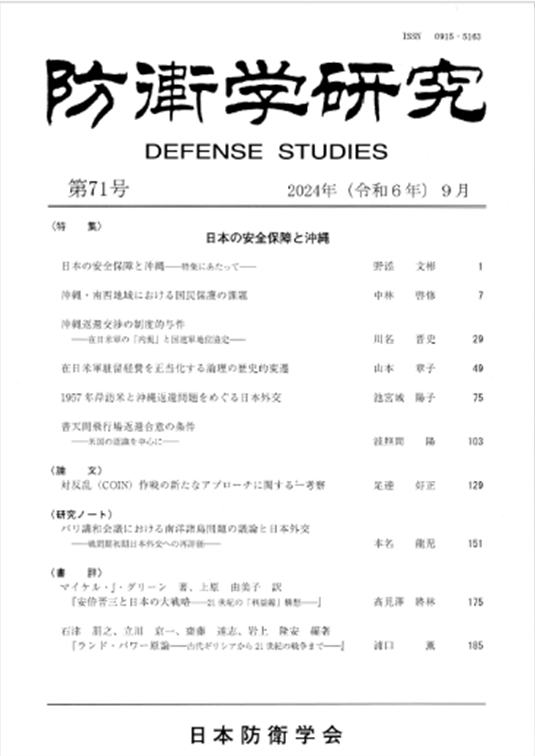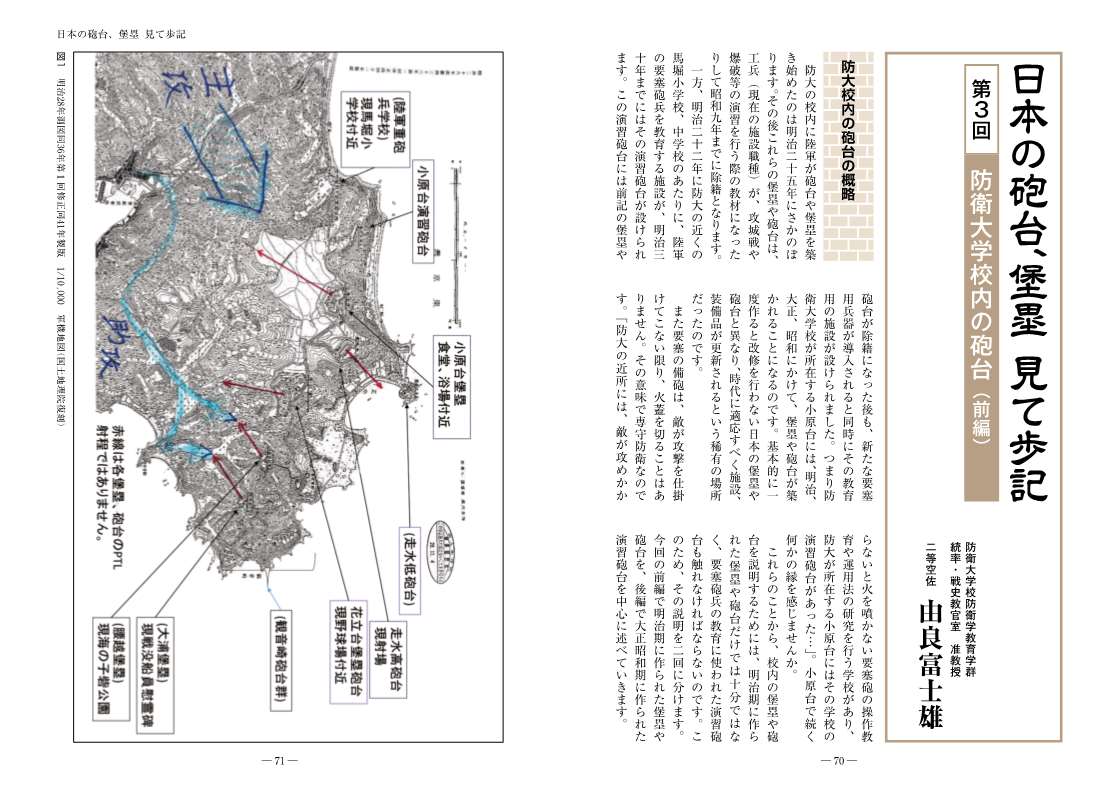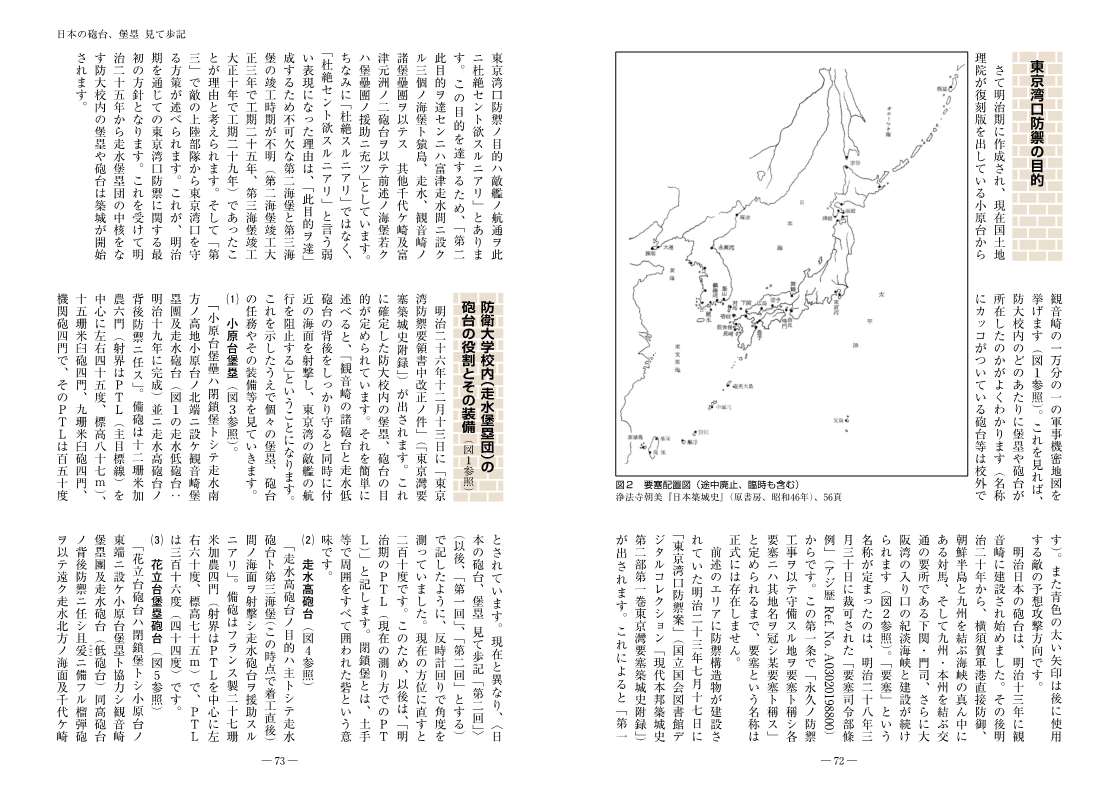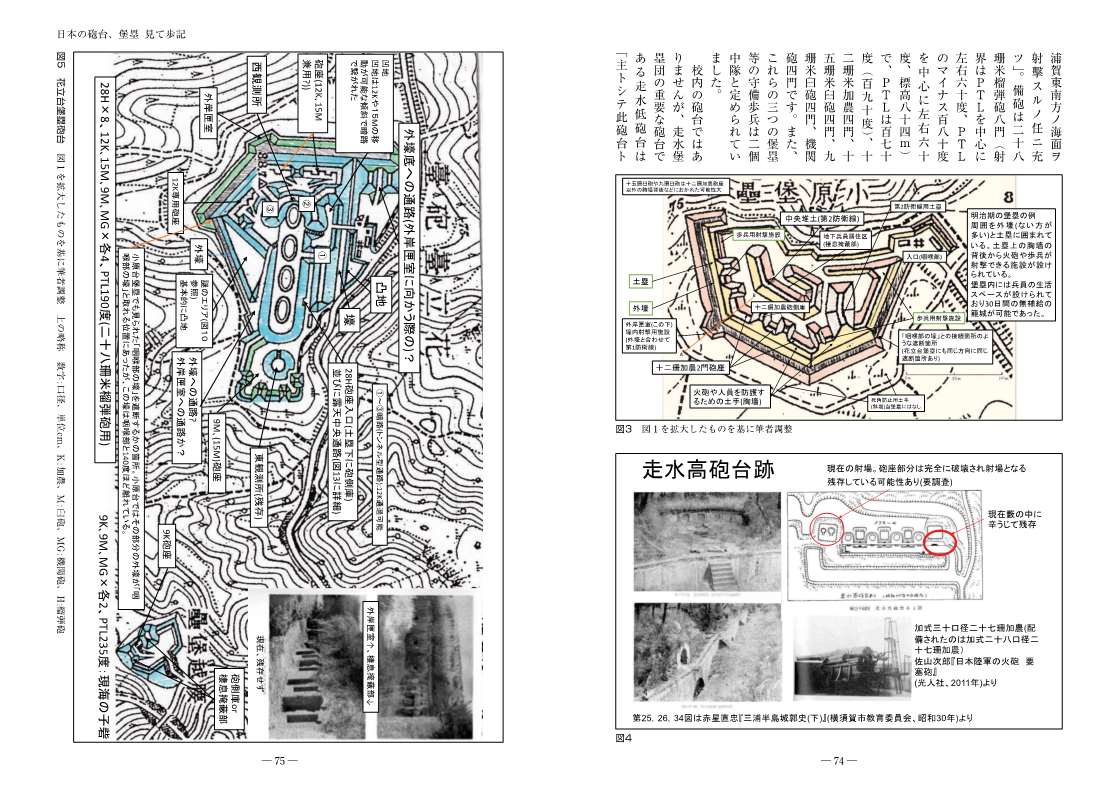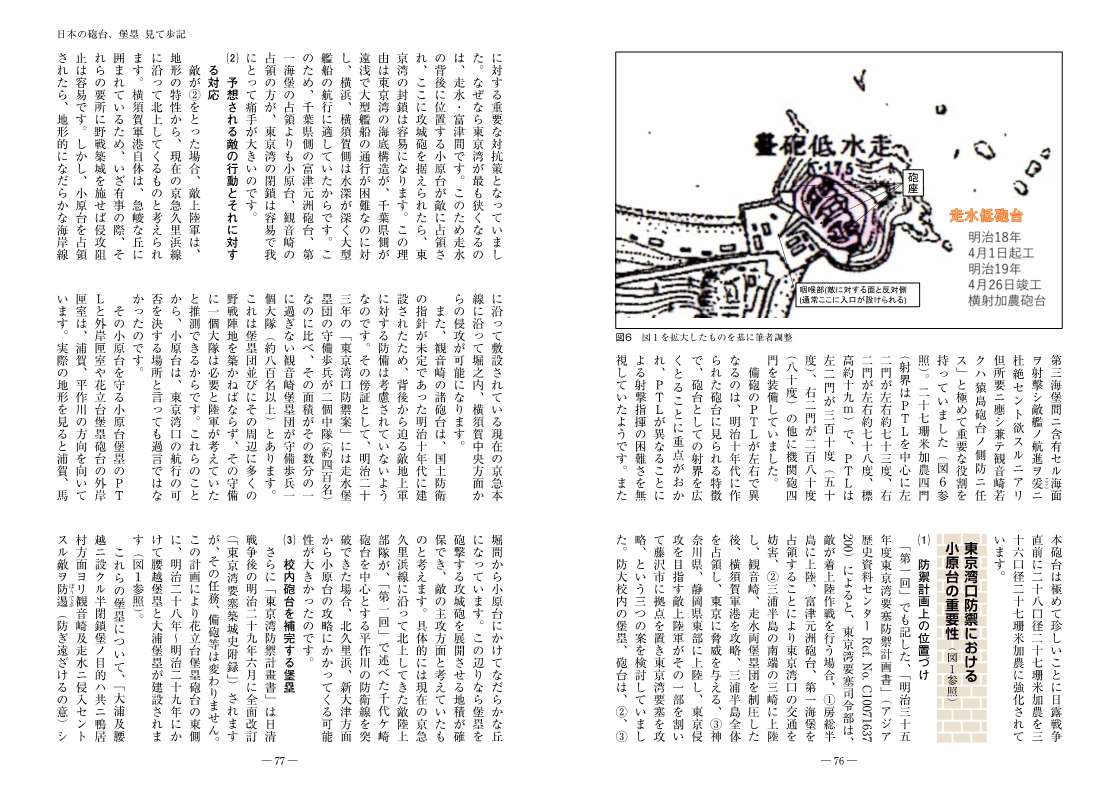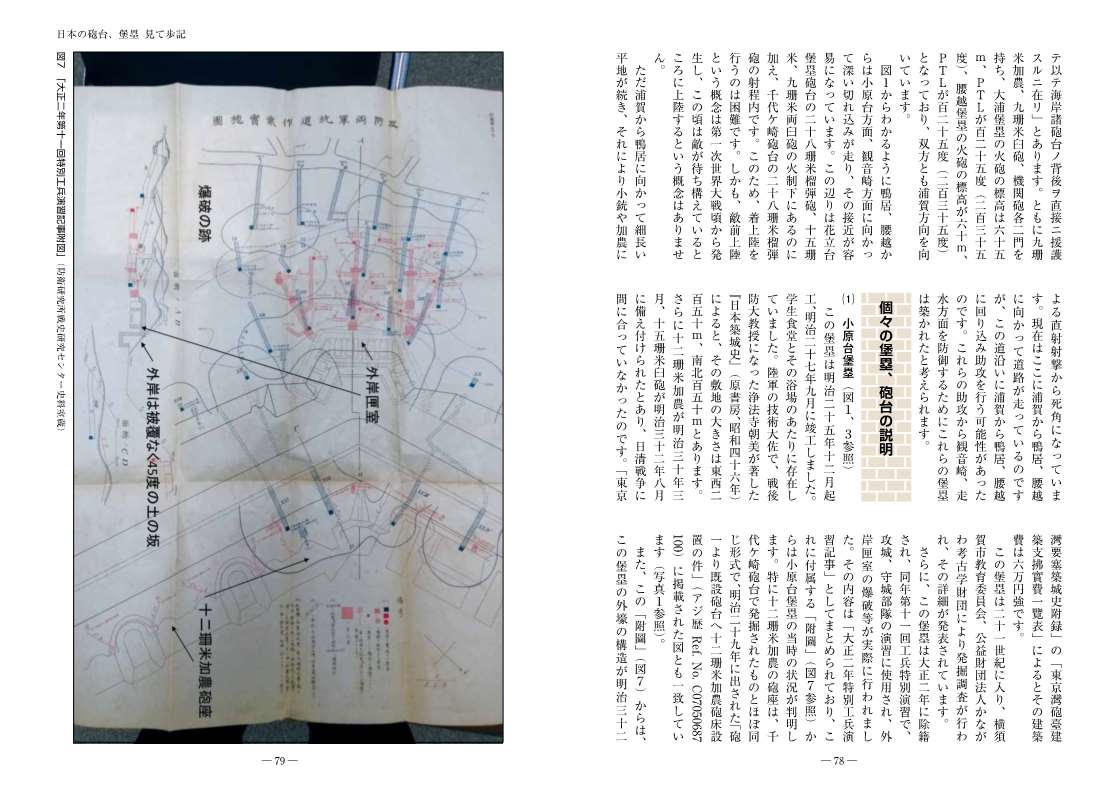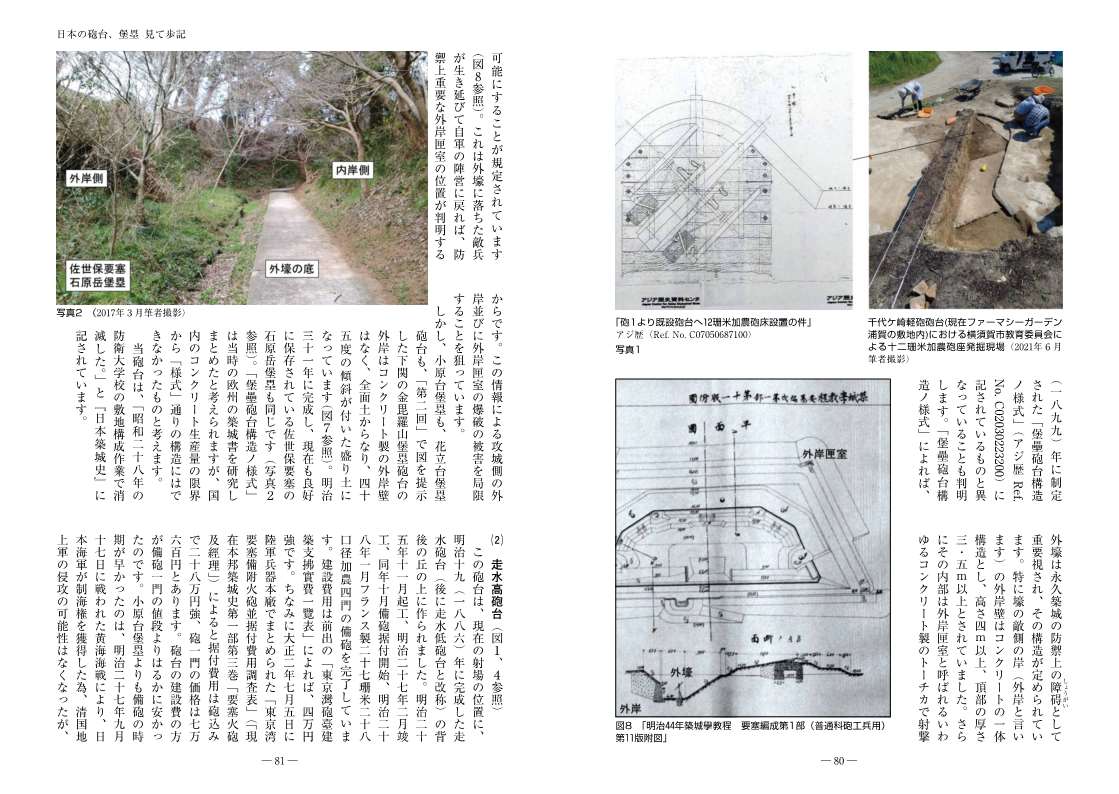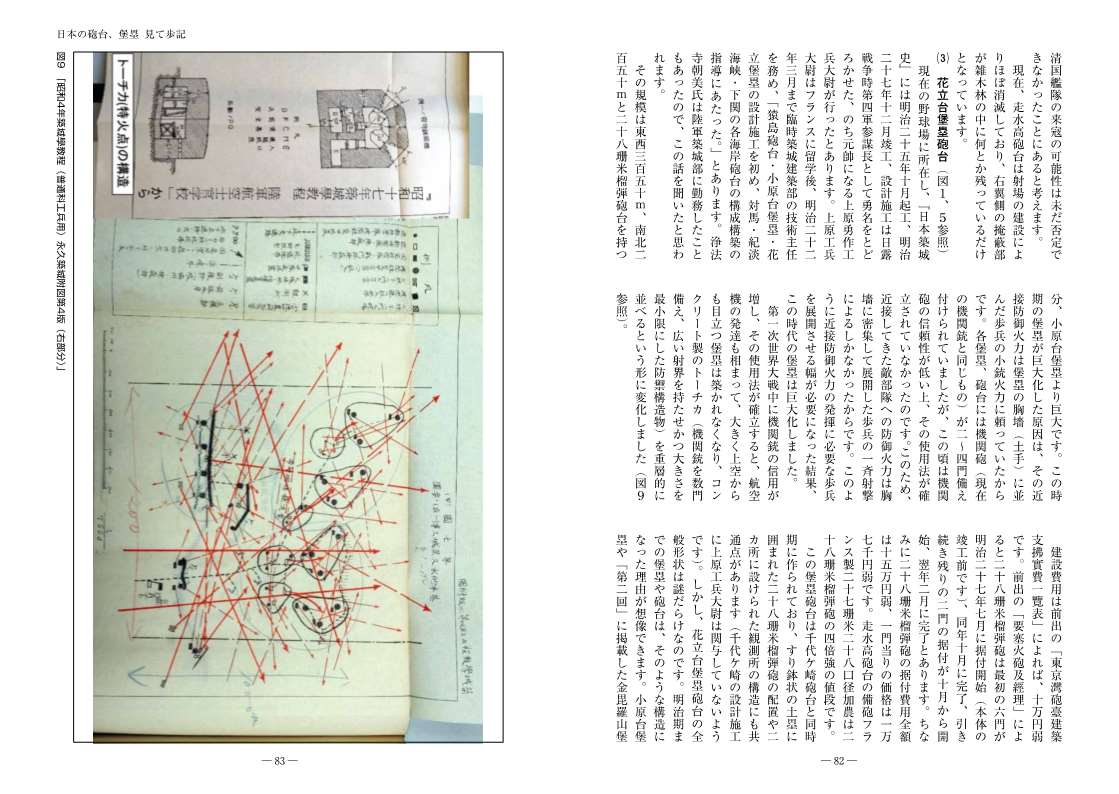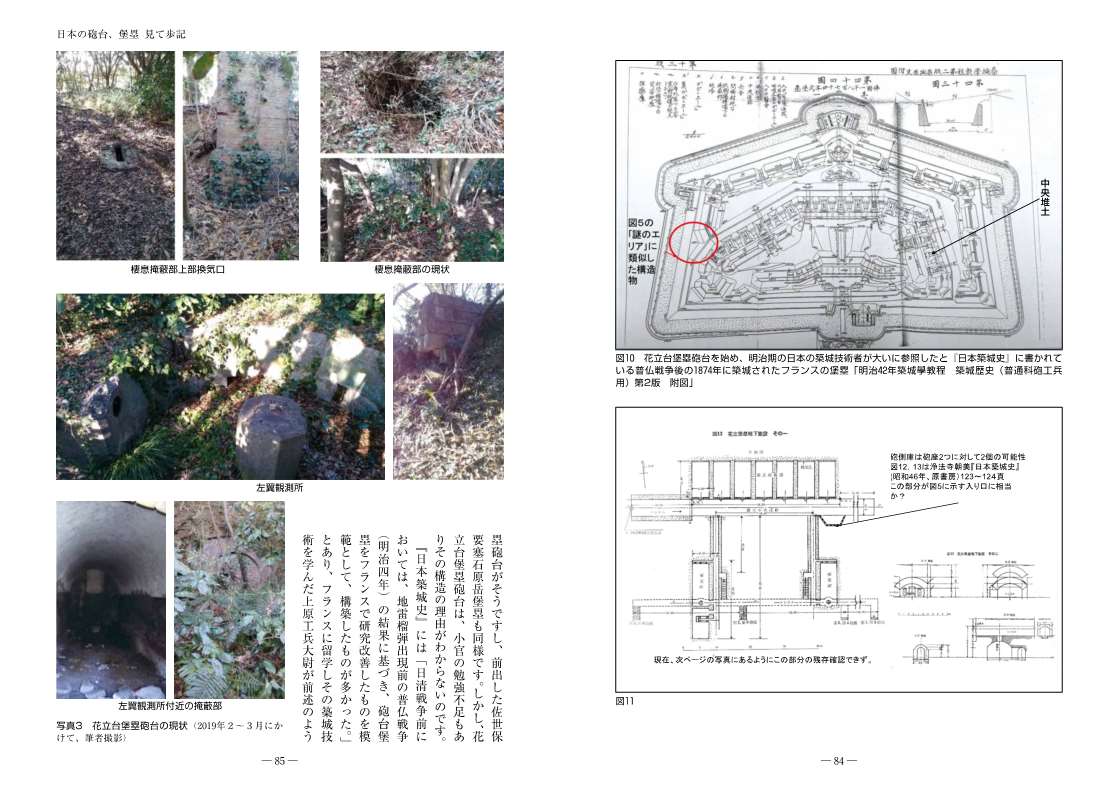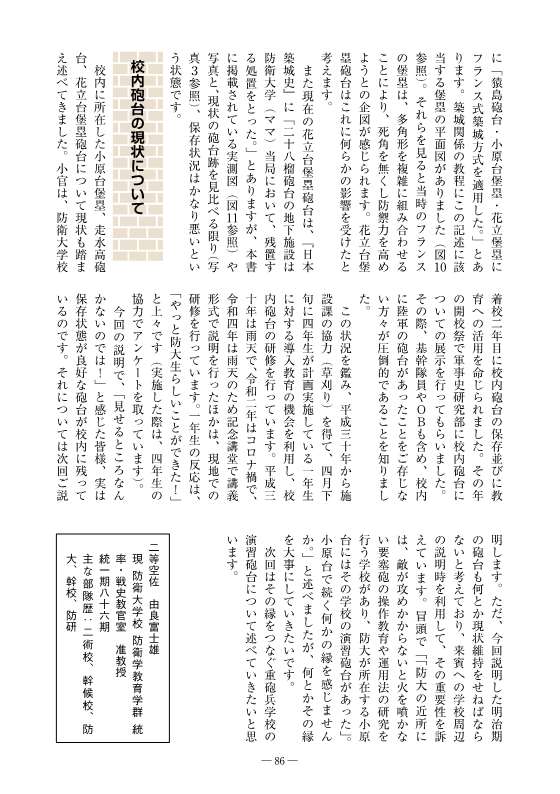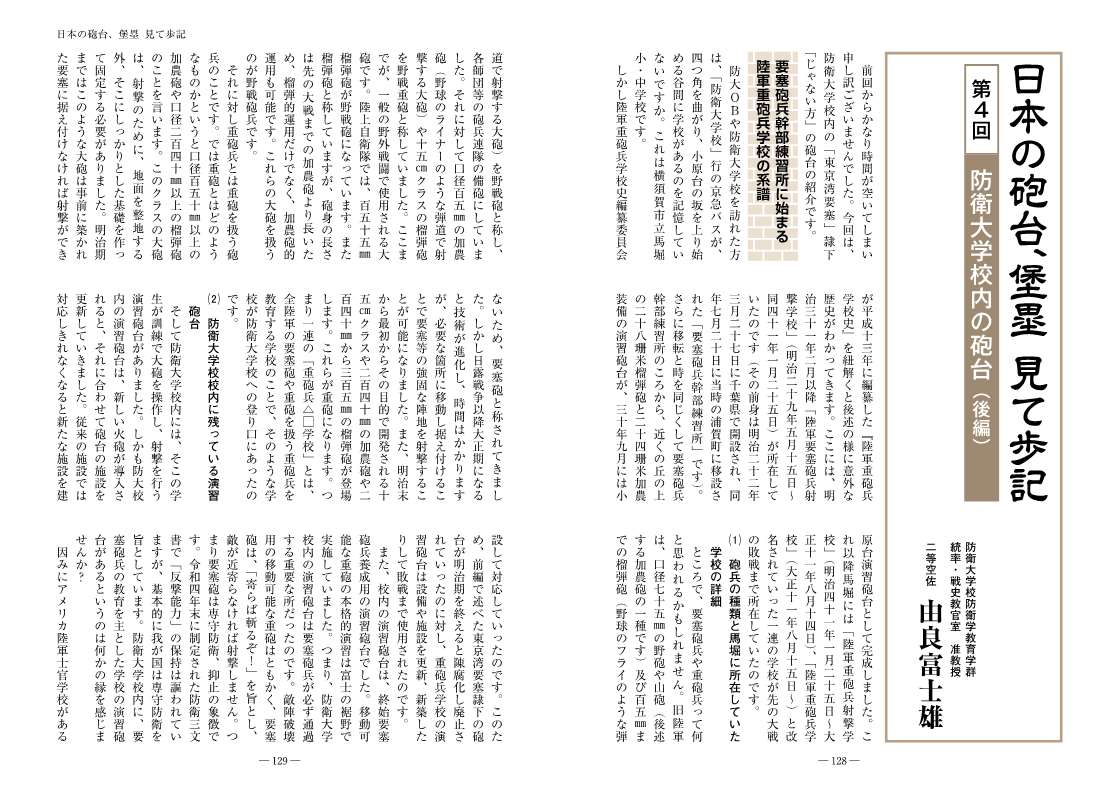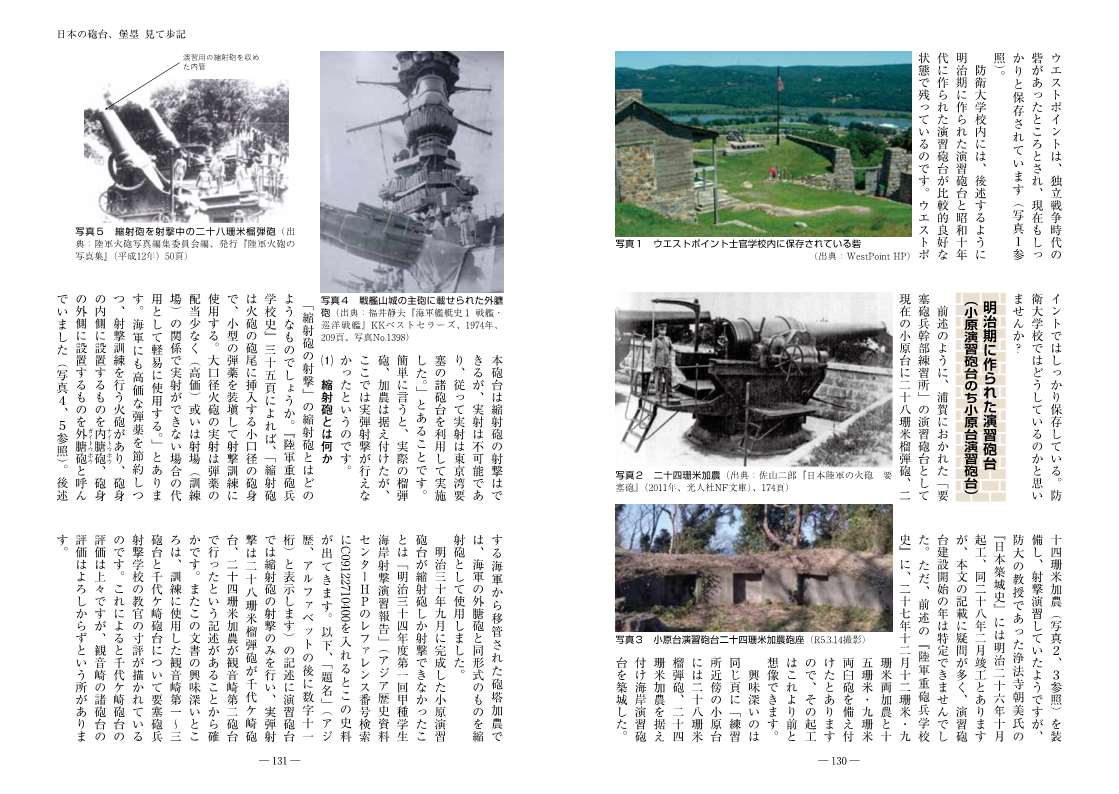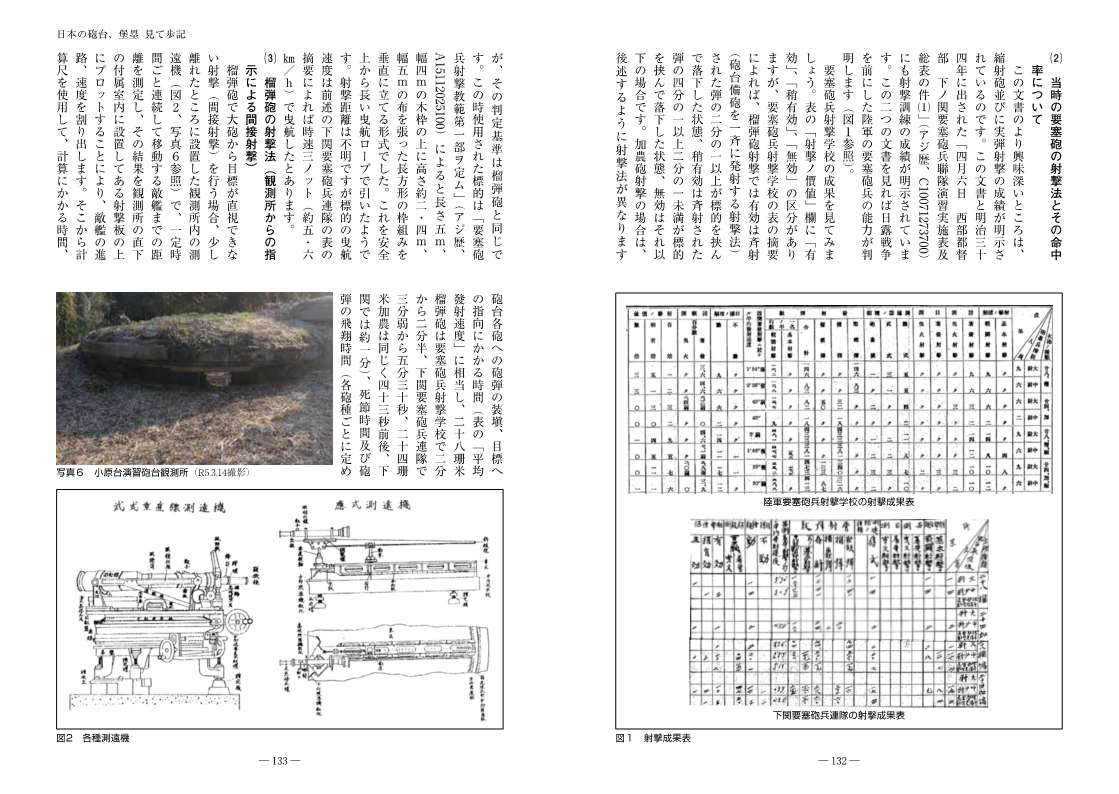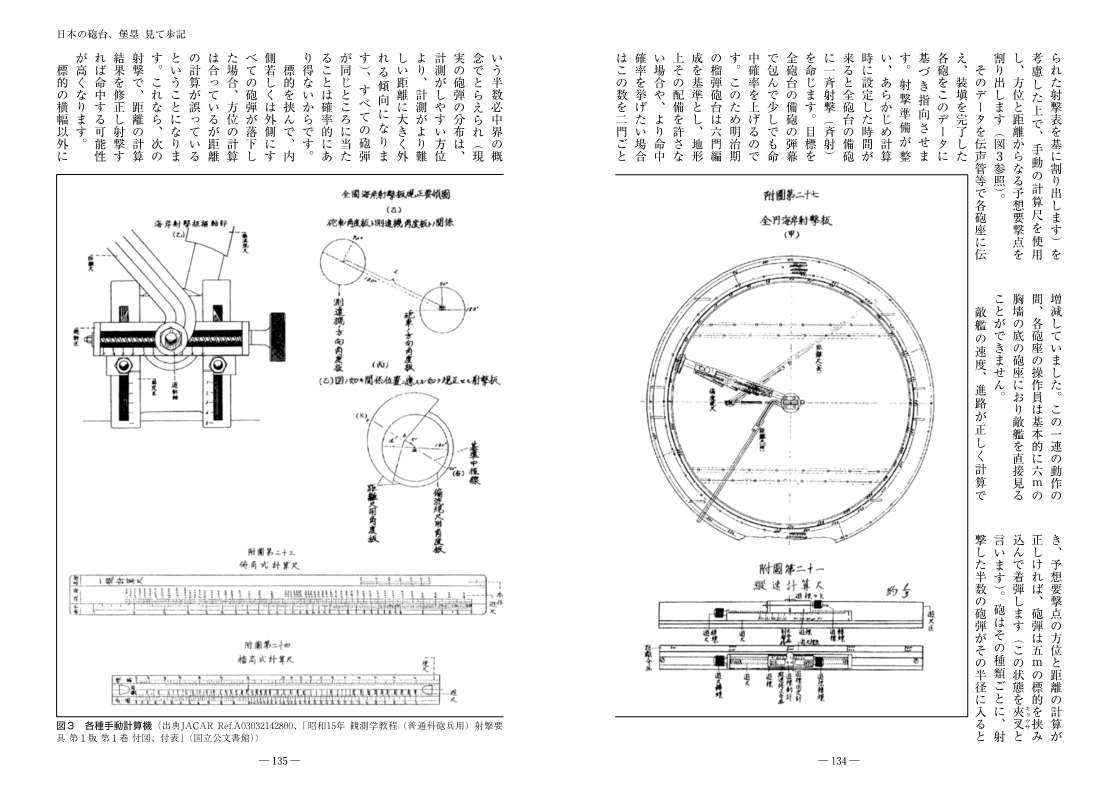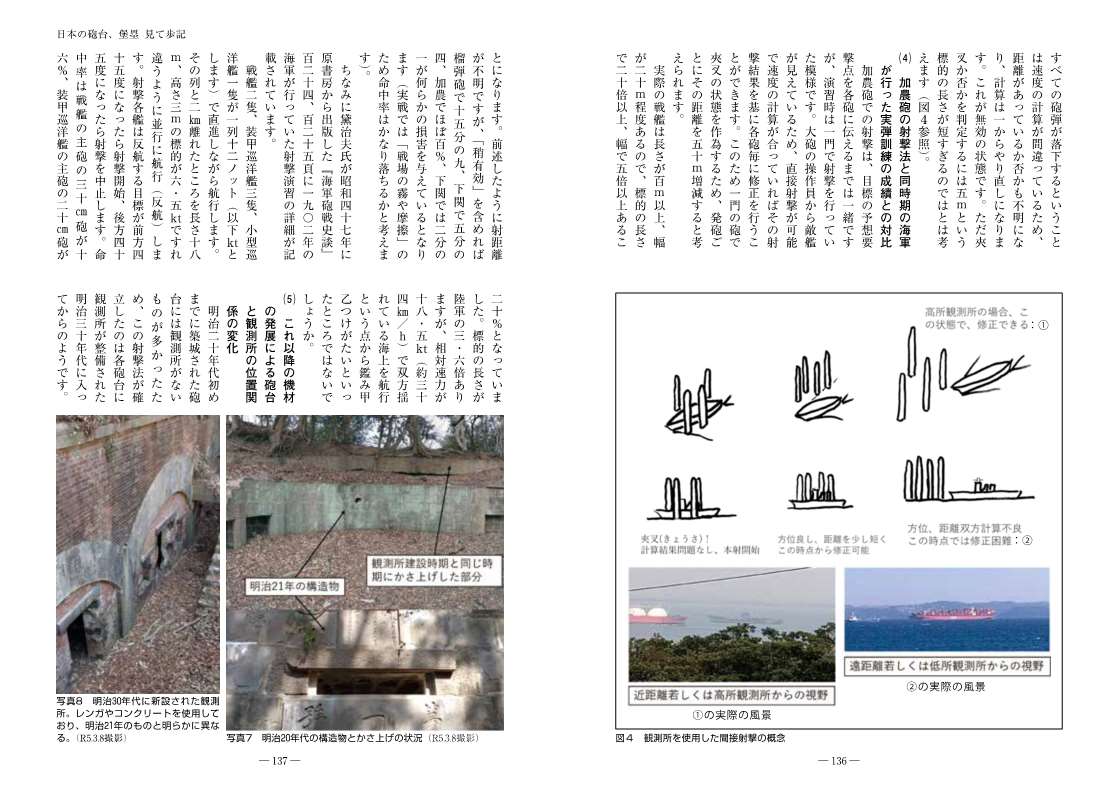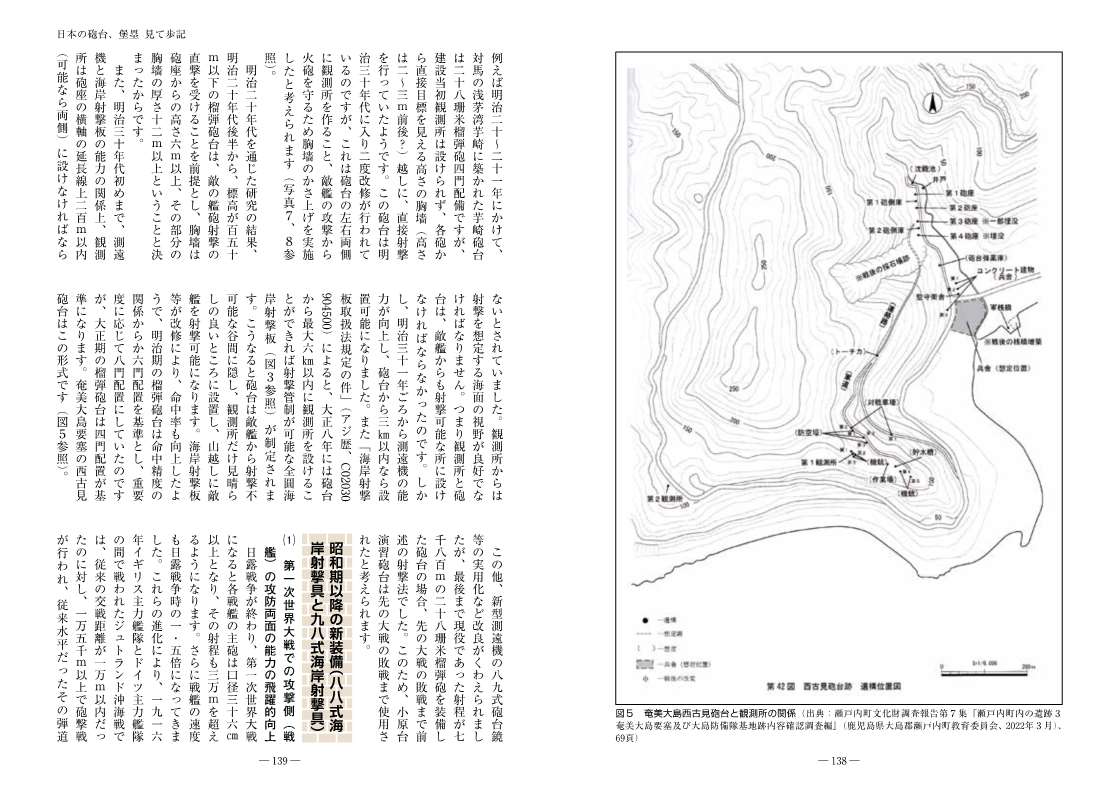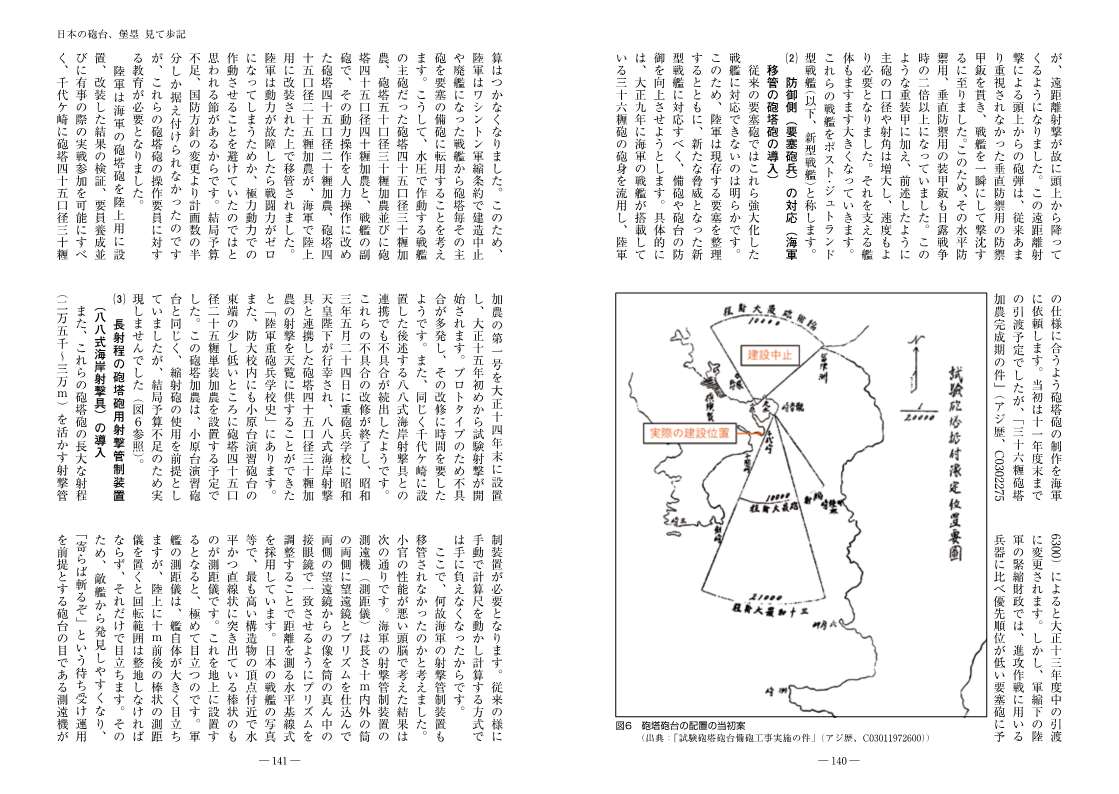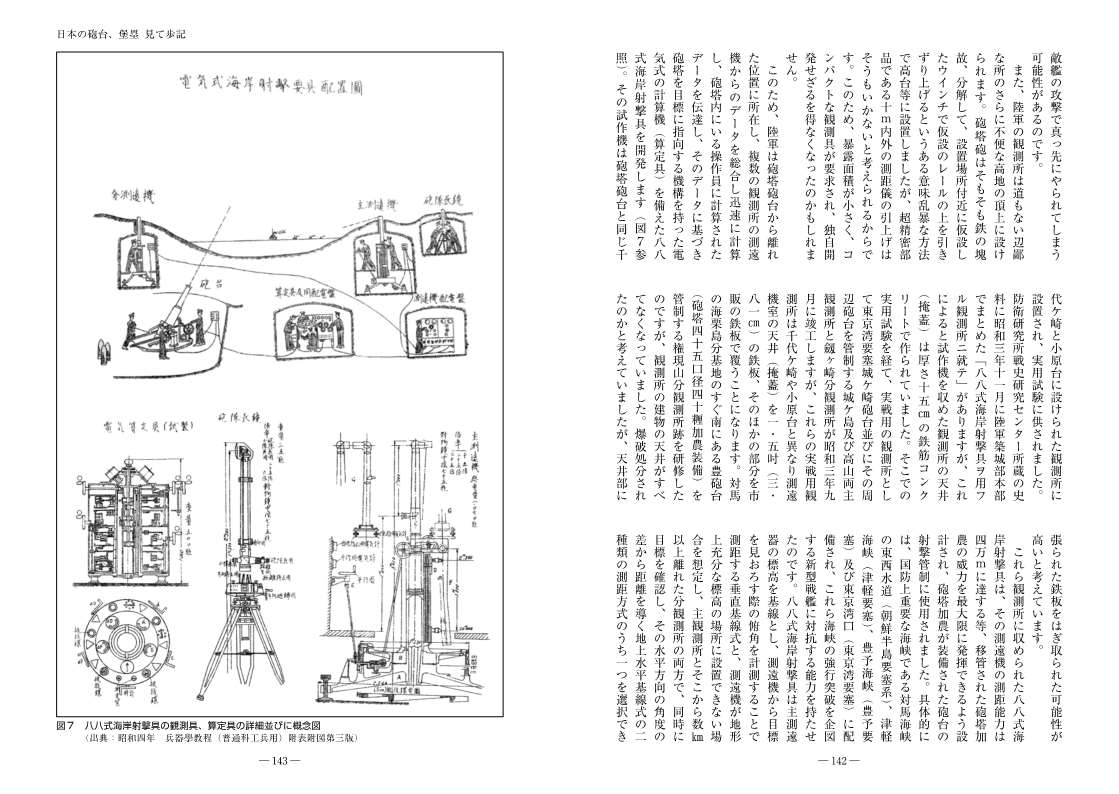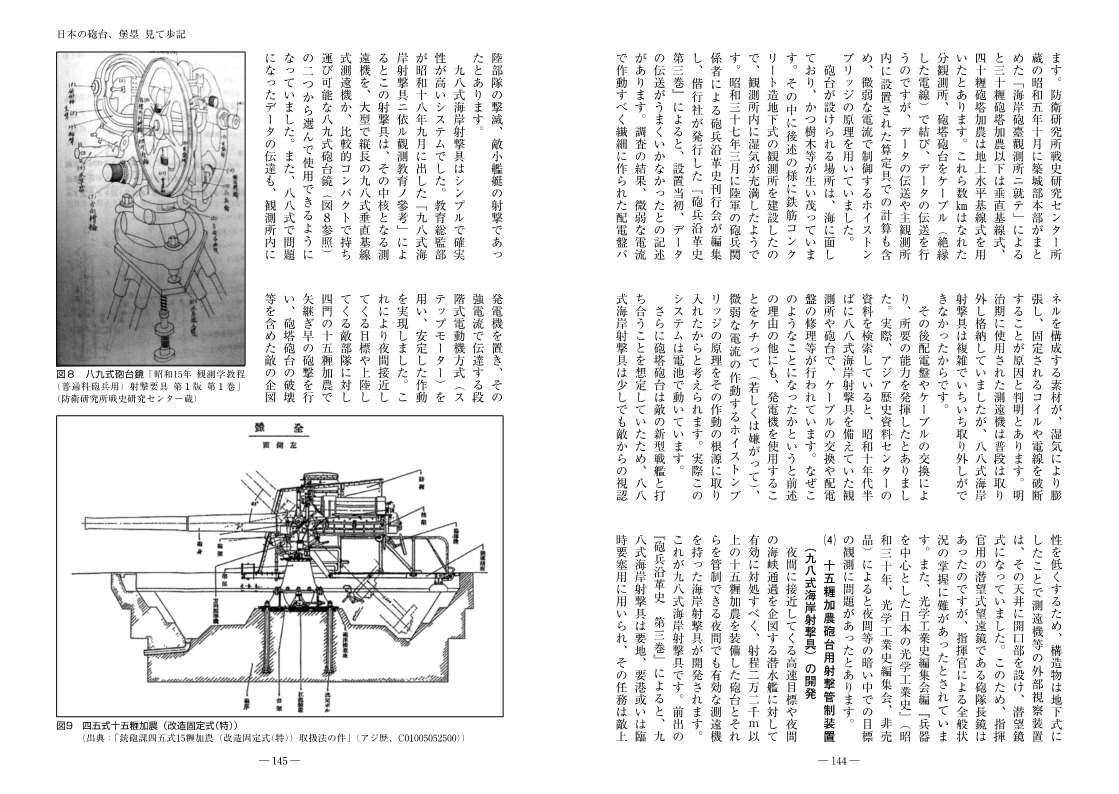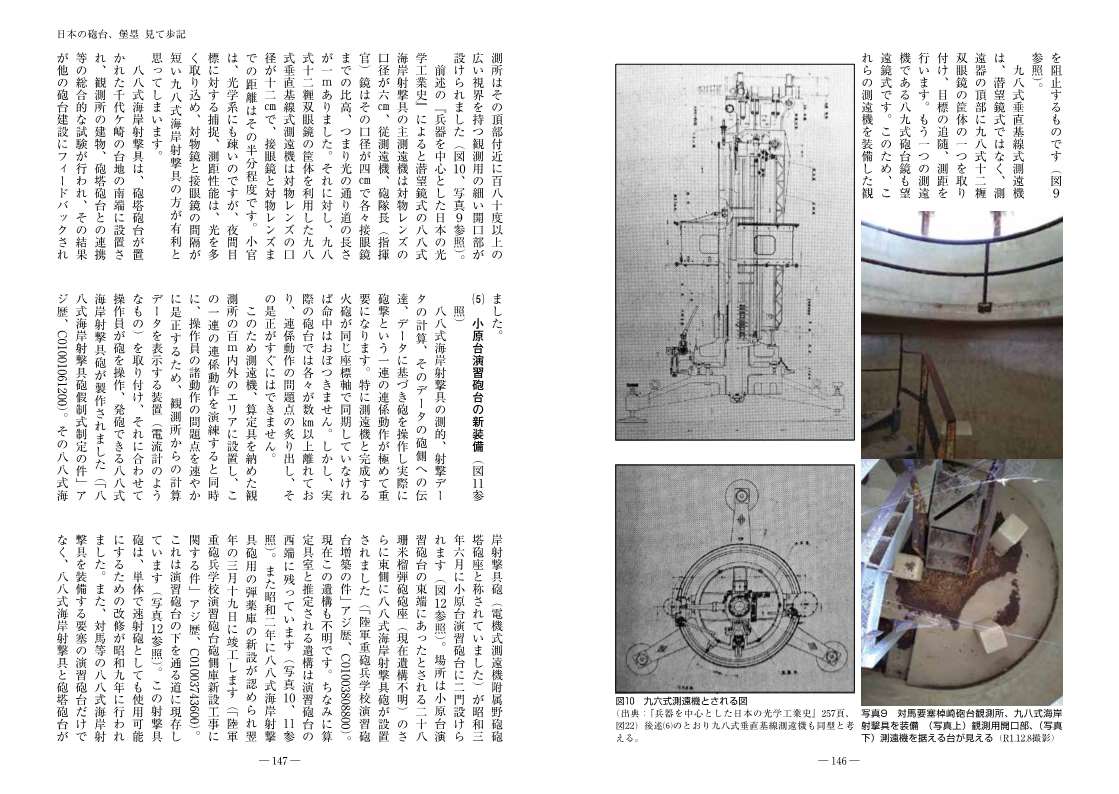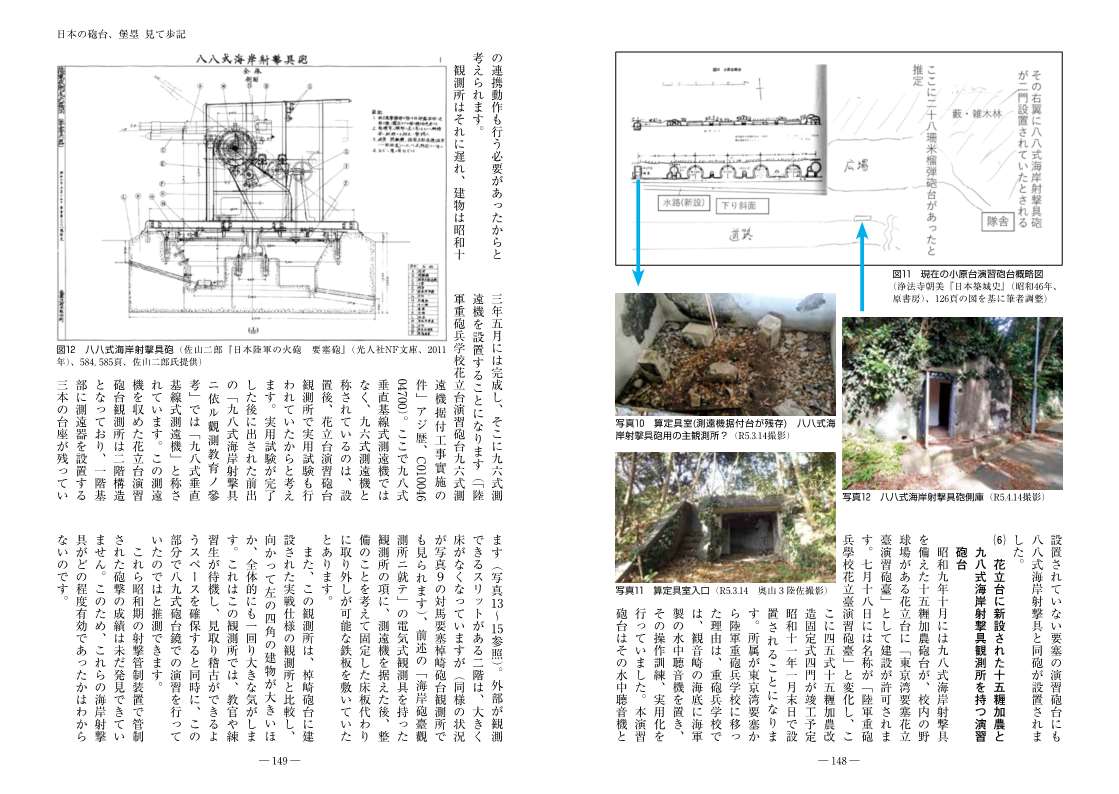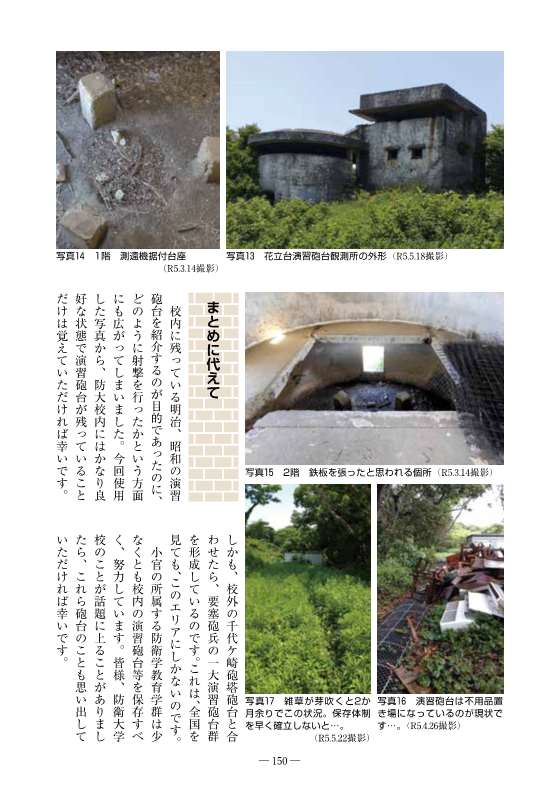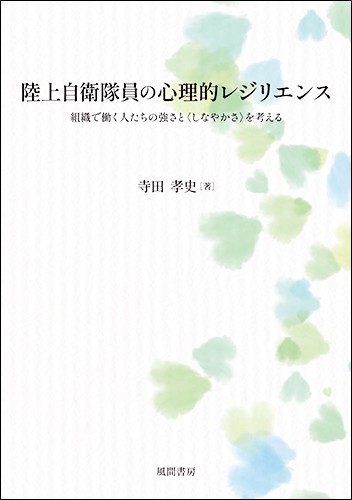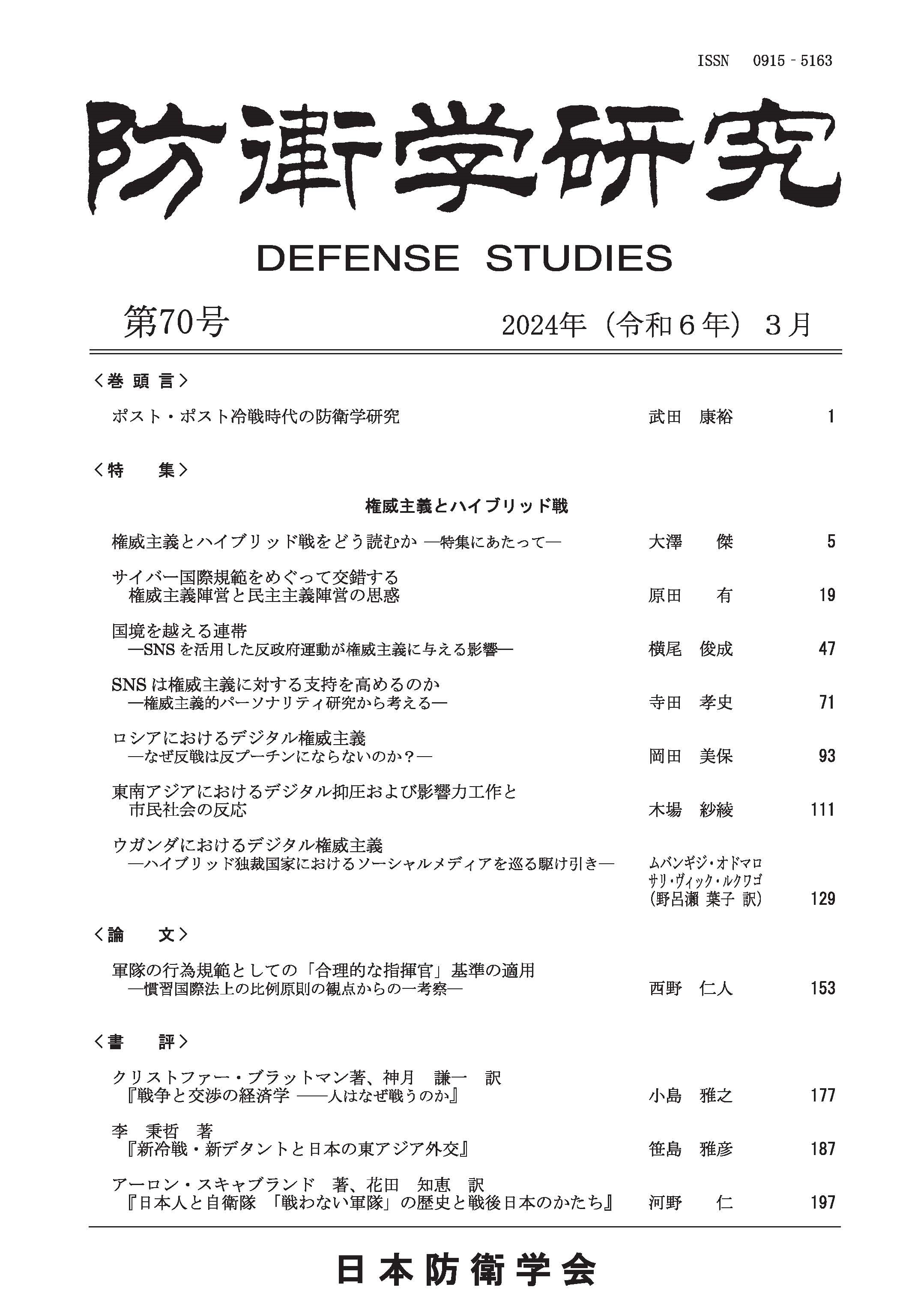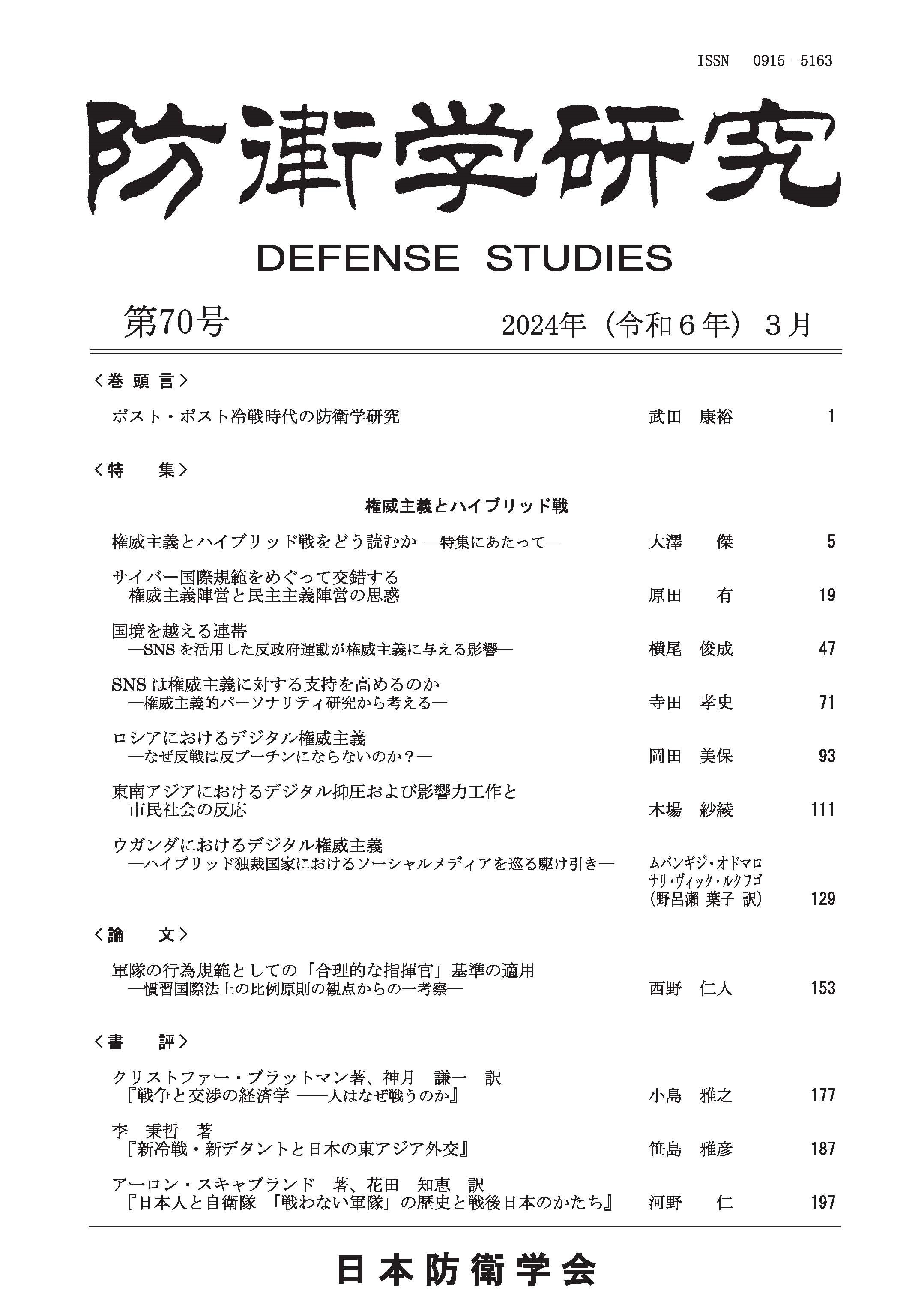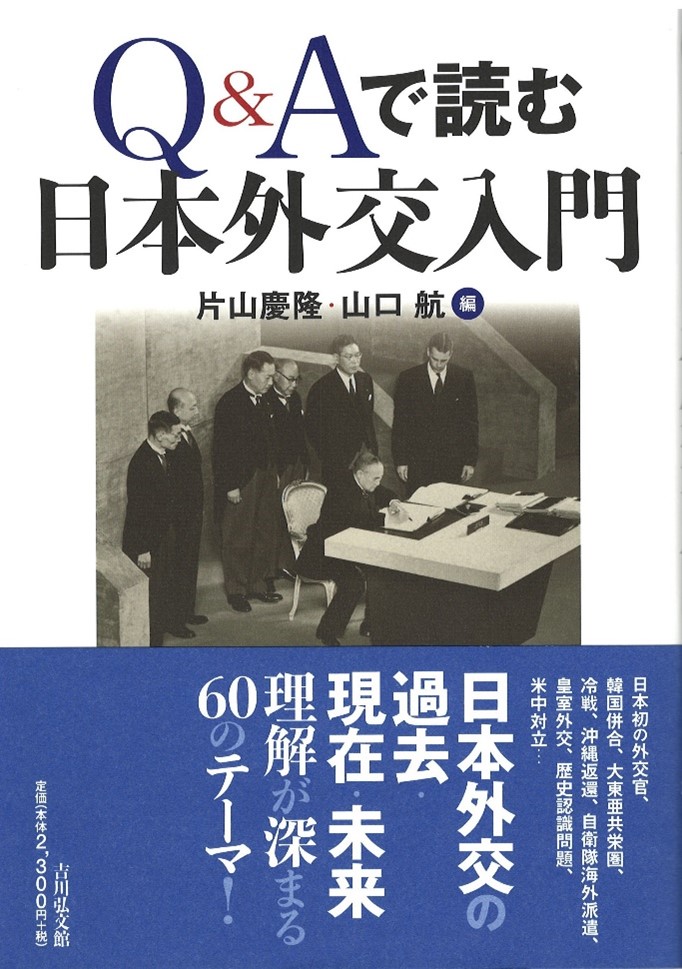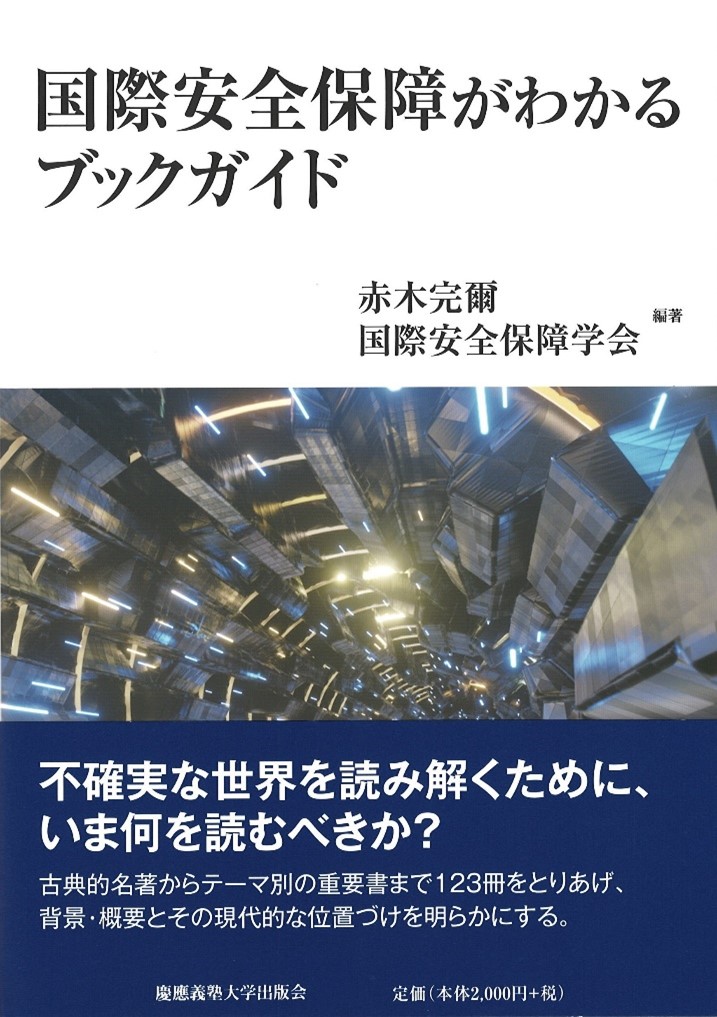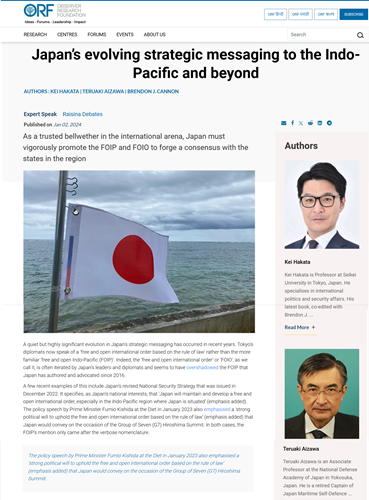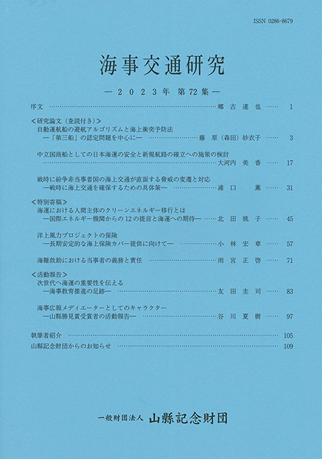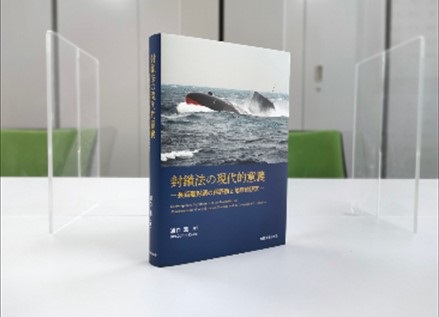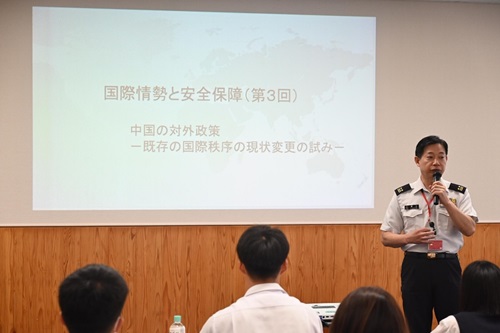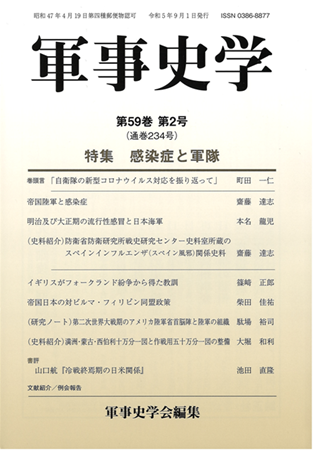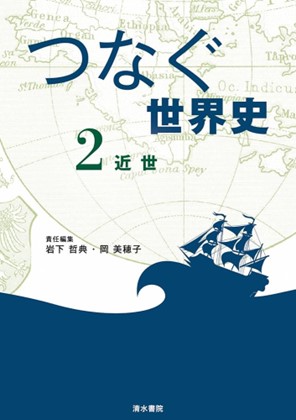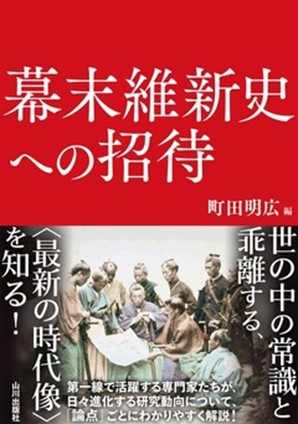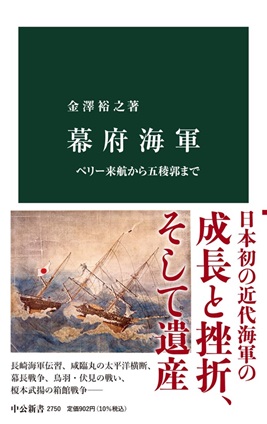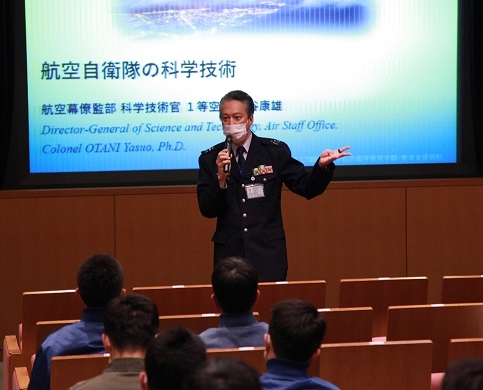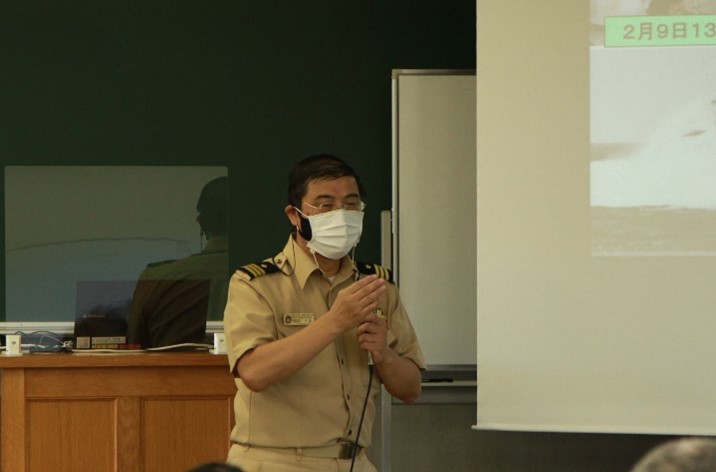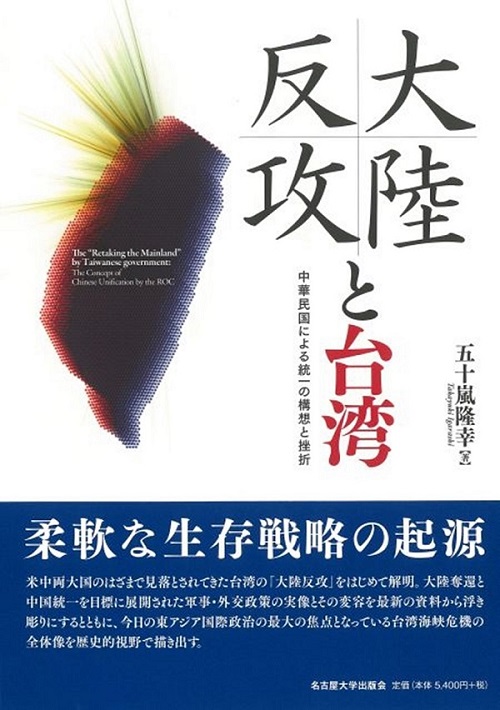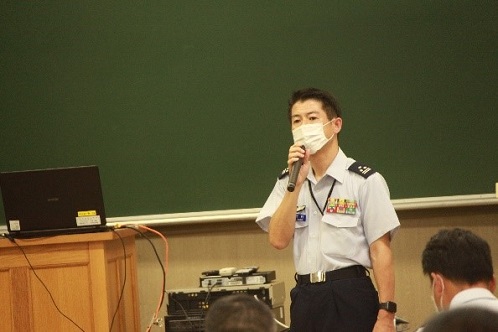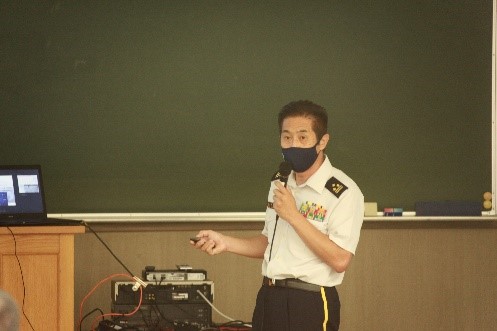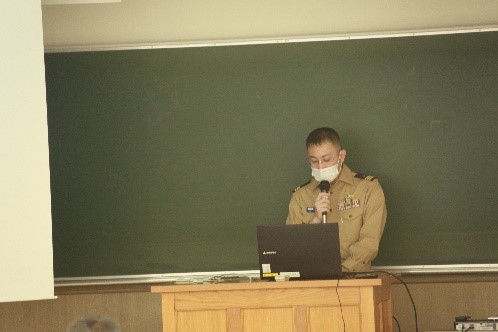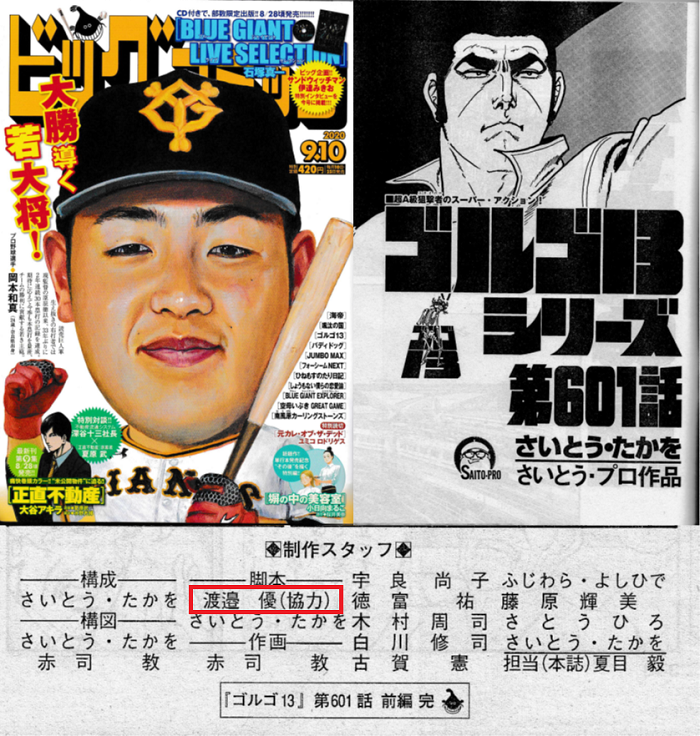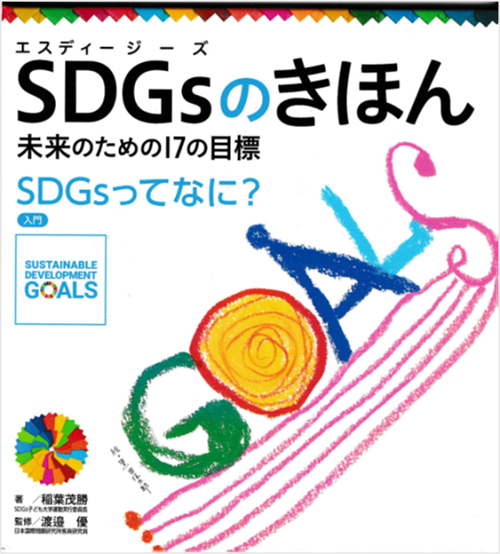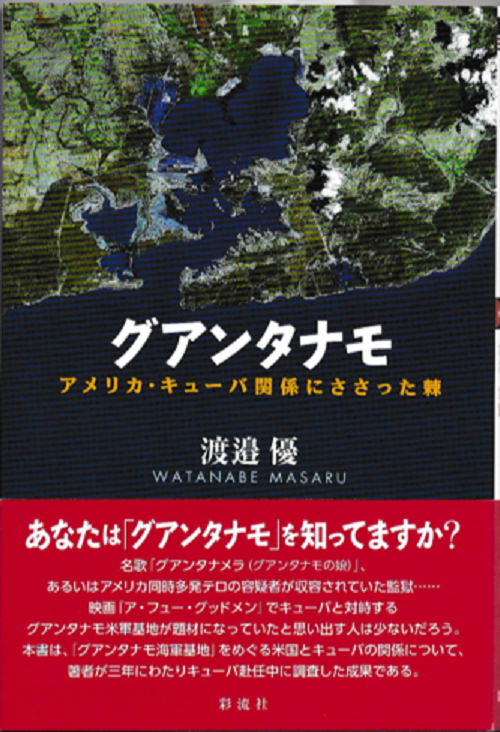2025/12/15 小橋 史行
〇論文等タイトル及び掲載媒体
1.査読論文
Ⅷ Japan, GLOBAL VISION OF FREE AND OPEN SPACES Creating Connectivity in
the Modern World, Observer Research Foundation& Heritage Foundation,
August 2025, pp. 136-146.
(内容)
自由で開かれたインド太平洋(FOIP)の軌跡と今後の展開について提言した。
2.論説
「強国ドイツを覚醒させたプーチン、4年後に予想されるロシア侵攻に備えを本格化 軍備拡充・核シェルター整備から海外移住まで、国民に広がる安保意識
」
日本ビジネスプレス、 2025年8月。
(内容)
ロシア侵攻に備えを進めるドイツの現状について解説した。
備 考
本件は、論文投稿時に部外意見発表手続きを実施済み。